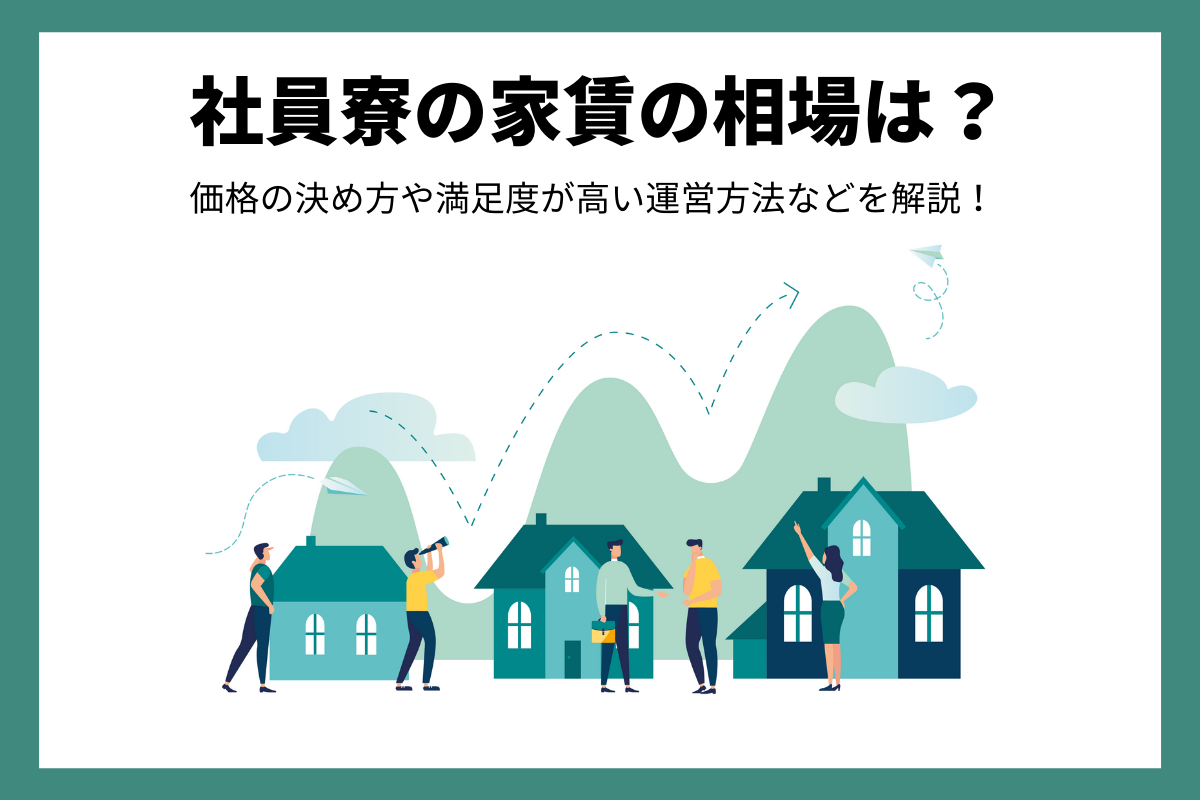人材不足が叫ばれる昨今、福利厚生を充実させて人材定着を図る企業も増えています。社員寮や社宅も福利厚生のひとつで、転勤者や新入社員にとっても魅力的な制度です。この記事では、社員寮の運用を始めるにあたって気を付けるべきポイントをご紹介します。
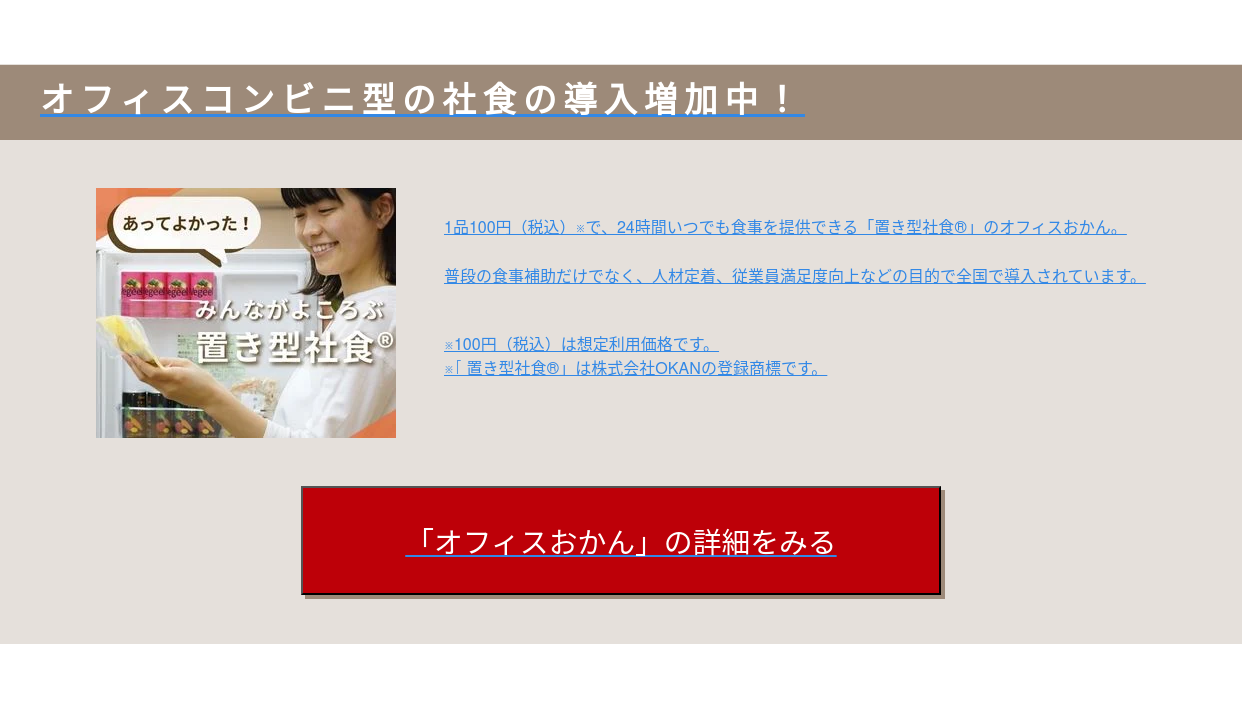
社員寮・社宅とは?
社員寮とは、企業が従業員に対して比較的安い価格で貸与する住宅のことです。単身者向けの物件を「社員寮」、家族向けの物件を「社宅」と呼び分けたり、単身赴任寮・男性寮・女性寮などに分けて用意したりするケースもあります。いずれも従業員の住環境について補助する制度のひとつです。
企業が社員寮を導入する目的は、主に福利厚生を充実させることや、転勤への対応を柔軟にさせることにあります。社員寮や社宅によって住環境が確保されていることは、遠方からの求職者にとっても魅力的なポイントといえるでしょう。
人手不足が叫ばれる昨今では、従業員満足度を高められる福利厚生制度への注目が高まっています。社員寮は個人で家を借りるよりも安価なことから、企業に対する従業員の満足度が高まり、離職率の低下にもつながると考えられます。
社員寮の形態は主に2種類
社員寮の形態には、社有型と借り上げ型の2種類があります。ここでは、それぞれのメリット・デメリットを見てみましょう。
社有型
社有型とは、企業が物件を所有している社員寮のことを指します。ある程度まとまった戸数でつくられることが多く、その物件に住む人は基本的に同じ企業の従業員となります。
土地や寮自体が企業の資産となるため、経費として計上できるメリットがあります。一方で、土地・建物の購入や建設費、管理費、固定資産税など大きなコストがかかることは、デメリットといえるでしょう。コストが大きいことから、大企業で取り入れられることの多い形態です。
借り上げ型
借り上げ型とは、企業が不動産会社から賃貸物件を借り上げて、従業員に提供している社員寮のことを指します。建設費や管理費といったコストが不要で、目的に合ったタイミングや場所で必要な戸数を準備しやすいことがメリットです。
しかし、1件ごとに物件探しや契約・解約等の手続きが必要であったり、物件内でトラブルが発生すると、借主である企業にペナルティが課されたりすることには注意が必要です。
社員寮の家賃相場
家賃設定はどれくらい?
2021年における新入社員の初任給平均(大学卒)は22万5400円であることや、一般的に「家賃は給料の30%までに抑えるのが望ましい」と言われていることを意識して検討すると良いでしょう。低価格な家賃で生活できることは、従業員にとって大きなメリットだと言えます。
出典:「令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2021/index.html)(2024年5月9日に利用)(調査主体:厚生労働省、調査対象:日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づく16大産業のうち5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所及び10人以上の常用労働者を雇用する公営事業所から、都道府県、産業及び事業所規模別に無作為抽出した56,465事業所に実施した調査、単一回答、集計計測期間:2021年7月。)
企業から見た社員寮の運営メリット
社員寮・社宅は従業員にとってメリットの大きい制度だと思われがちですが、企業にとってのメリットもあります。
節税につながる
給与として住宅手当を支給するのではなく、福利厚生制度として企業が賃料を支払えば、福利厚生の経費として計上できるため節税につながります。
従業員満足度の向上
社員寮・社宅は一般的な家賃よりも低価格で住めるため、結果的に従業員満足度の向上が期待できます。
特に、新天地での物件探しや手続きの手間が減らせるため、転勤希望や転勤の打診に快諾する従業員が増えると考えられます。
従業員同士のコミュニケーション
同じ物件に自社の従業員が多く住んでいる社員寮・社宅であれば、自然と従業員同士の交流も増えるでしょう。所属部署を超えたコミュニケーションが生まれやすいため、業務がスムーズに回りやすくなると考えられます。
企業イメージアップ
社員寮・社宅は福利厚生制度の一つです。取引先や求職者に対しても「福利厚生が充実している企業である」というアピール材料となり、企業イメージがアップします。
社員寮を作る際に注意すべきポイント
実際に社員寮をつくる際には、どういった点に気を付ければよいのでしょうか。ここでは、注意すべきポイントをご紹介します。
まずは規定をつくる
まずは、運営や入居条件に関する社内規定を定める必要があります。主な内容は次のようなものが挙げられます。
規定の主な内容例
- 入退寮に関するルールや手続き方法
- 年齢制限など入寮資格
- 入寮期限
- 家賃(寮費)の金額や支払方法
- 施設の管理体制
- 備品や鍵の破損・紛失による修繕費・弁償代などのルール
- 部外者の立ち入りについて
- 外泊について
- 禁止事項(門限、部屋の改装など)
大切なのは、社員寮をつくる目的を果たせるルールづくりをすることです。社員寮は共同生活となるため、共用施設や設備を大切に扱えるような決まりをつくっておくとよいでしょう。また、従業員に対し過干渉になってしまわない範囲で規定を定めるように気を付けましょう。
家賃だけでなく立地も重要
従業員にとって社員寮は、一般的な賃貸物件よりも低価格で住めるのが魅力ですが、家賃だけでなく物件の間取りや立地も重要になります。
社員寮の立地を決める際は、職場までの通勤のしやすさや交通の利便性、周辺環境を加味しながら、従業員にとって暮らしやすい物件を選ぶよう心がけましょう。
セキュリティ対策を充実させる
「安いがセキュリティに不安がある物件」よりも「多少高くてもセキュリティ対策がされている物件」の方が安心して暮らせます。従業員の暮らしを守ることは、ワークライフバランスの実現にもつながりますので、セキュリティ面が充実しているかどうかも意識しましょう。
食事環境を整える
社員寮に食堂を備え付けて、食事環境を整えるのもよいでしょう。食堂をつくる場合は、食事の時間や配膳方法、片付けのルール、食事が不要な場合の連絡方法、費用についてなどを規定に盛り込んでおく必要があります。
整理整頓・清潔さのルールを定める
共有部・共有物の整理整頓や、清潔さを保つためのルールを定めておくと、居住者全体にとって良い生活環境が保たれるようになります。社員寮は複数人での共同生活です。従業員が快適に暮らせるよう、企業側が最低限のルールとマナーを規定で定めておくことも大切です。
近年の社員寮事情
実際、どのくらいの企業が社員寮を運営しているのでしょうか。ここでは、社員寮事情を見ていきましょう。
国土交通省が発表している「建築着工統計調査」の給与住宅(会社や官公庁が給与の一部として与える住宅)の新設着工数を見ても、2015年度〜2017年度に比べて2018年度〜2020年度は増加の傾向が見られます。
一時は減少を続けていた社員寮ですが、人材不足や従業員同士のコミュニケーション不足などの課題を解消する福利厚生制度の1つとして、再注目されているのかもしれません。
出典:「建築着工統計調査」(国土交通省)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&query=%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%80%80%E6%96%B0%E8%A8%AD%E7%9D%80%E5%B7%A5%E6%95%B0&layout=dataset&toukei=00600120&bunya_l=08&tstat=000001016965&cycle=7&month=0&open_date=202101&tclass1val=0&metadata=1&data=1)(2024年5月8日に利用)
満足度の高い社員寮で働きやすい環境づくりを!
社員寮や社宅は従業員にとって満足度の高い福利厚生のひとつです。節税やイメージアップ、人材定着など企業側にも大きなメリットがあることから、導入が増えてきているようです。
従業員の住環境を整えることは、ワークライフバランスの実現にもつながります。これから社員寮や社宅の制度を整える企業は、居住者が快適に暮らせる仕組みを心がけ、より働きやすい環境づくりを行いましょう。