ストレス社会とうたわれる昨今、「○○ハラスメント」という言葉を聞く機会も多いでしょう。もし職場でハラスメントが起こると、被害者個人だけでなく企業にとってもリスクがあるので適切な対応が必要です。
この記事ではハラスメントとは何を指すのか、パワハラ・セクハラ以外のハラスメントの種類についても解説します。また企業としてどのような対応が必要なのか紹介します。
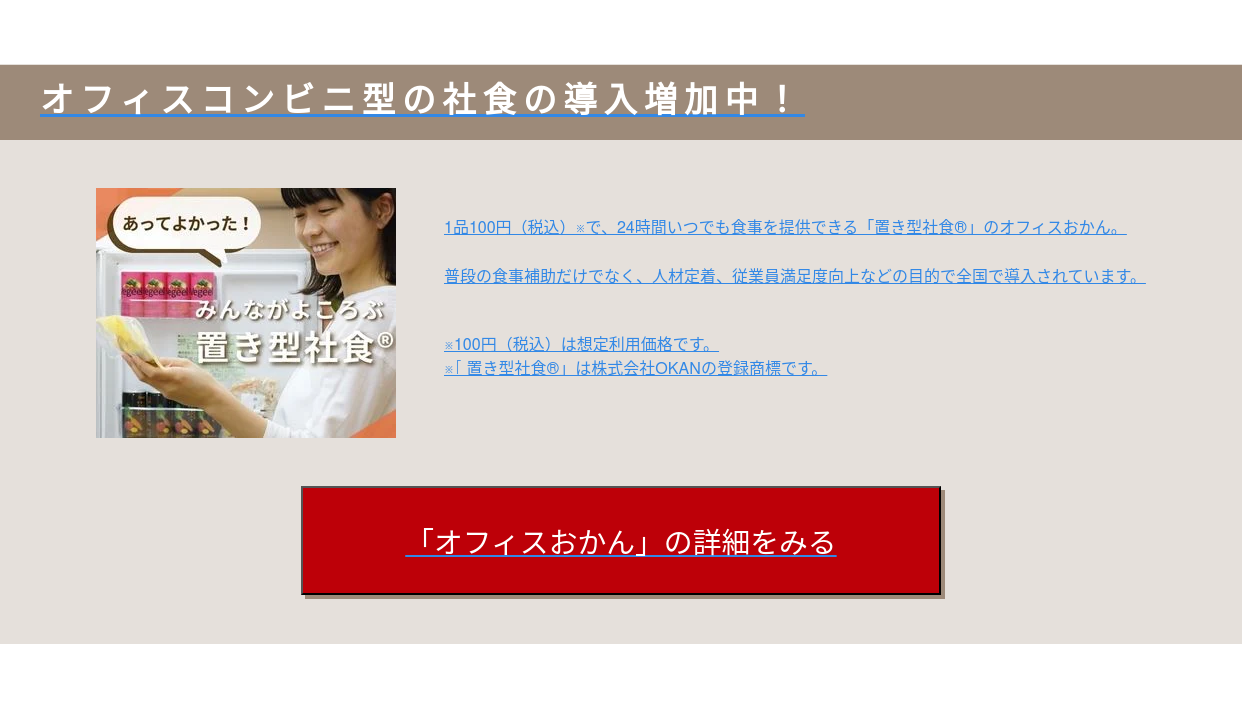
ハラスメントの定義とは
ハラスメント(harassment)は広義には「人権侵害」を意味する言葉です。故意かそうでないかに関わらず、相手が不快感や不利益を被る迷惑行為をして尊厳を傷つけることを指します。性別、年齢、職業、宗教、人種、国籍、身体的特徴といった、属性や人格を攻撃するような言動によるいじめ・嫌がらせはハラスメントに該当するのです。
当然ハラスメント行為は社会的に許されるものではありません。しかし近年、職場におけるセクシャルハラスメント(セクハラ)やパワーハラスメント(パワハラ)、マタニティハラスメント(マタハラ)やパタニティハラスメント(パタハラ)などが大きな問題となっています。
「行為者(加害者)がどう思っているかに関わらず、相手(被害者)が不快だと感じたらハラスメントになる」というのも重要なポイントです。「嫌がらせのつもりではなかった」と行為者がハラスメントを行っていることに気付かないケースも多々見られます。
たとえば職場で仕事と直接関係のないことや、プライベートなことに対して過度に口を出すといった行為がパワハラに該当する可能性もあるので注意しましょう。
パワハラと指導の違い
業務上の合理的な理由により行われる指導や注意といった、客観的に正当化できる行為であれば基本的にパワハラには当てはまりません。指導や注意は「相手のために」行うことが目的なので、業務の改善や相手の成長を促せる期待ができます。
パワハラは「自分の思い通りにしたい」という目的で、相手を非難したり攻撃的な態度をとったり、自分の感情を優先にした嫌がらせ行為をすることです。業務上必要のないプライベートや人格を否定するような発言をして相手の尊厳を傷つけ、精神的な苦痛を与えることなどがパワハラにあたります。
指導とパワハラの違いを理解して適切な指導を行うことで、活気のある職場になり退職防止にもつながるでしょう。
代表的なハラスメントの種類を解説
企業内でハラスメントを発生させないためには、まずは基本的な知識を身につけることが大事です。ここでは職場で起こりがちな代表的なハラスメントを紹介します。故意であるかどうかに関わらず、以下のような行為をしている従業員に気付いた際は、すぐに対応策をとるべきです。
パワーハラスメント
パワーハラスメント(パワハラ)とは同じ職場で職務上の優位な立場を利用し、業務の必要範囲を超える注意や嫌がらせ、暴行など相手を傷つける行為をすることです。パワハラを受けた人は心理的ストレスを感じ、うつや適応障害などの精神症状が出たり、頭痛や不眠、胃痛など身体へ悪影響を及ぼしたりすることもあります。
厚生労働省によると、代表的な行為として以下の6類型が挙げられています。
“①身体的な攻撃(暴行・傷害)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい 暴⾔)
③⼈間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・ 無視)
④過⼤な要求(業務上明らかに不要なことや遂⾏ 不可能なことの強制、仕事の妨害)
⑤過⼩な要求(業務上の合理性なく、能⼒や経験 とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑥個の侵害(私的なことに過度に⽴ち⼊ること)”出典:厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd.html)(2024年5月11日に利用)
殴る蹴るなどの暴力行為や同僚の前での𠮟責などは、身体的・精神的な攻撃としてわかりやすい例でしょう。1人だけ別室に席を移す、飲み会に呼ばないなどは、人間関係からの切り離しになります。
また、他の人がやるべき仕事を押し付けて自分たちは帰宅する、運転手に営業所の草むしりだけを命じるなどは、過大・過小な要求に該当します。さらに、交際相手について執拗に問いただすといった行為は、個の侵害になるのです。
モラルハラスメント
モラルハラスメント(モラハラ)とは、相手に対して言葉やメールの文書、身振りや態度などによって精神的な苦痛を負わせる行為のことを指します。パワハラとは違ってあからさまな暴力や暴言ではないことが多く、周囲の人々が気付きにくいのが特徴です。
たとえば無視や仲間外れ、業務上必要な連絡をわざとしないなど、他者にはわかりづらい形で行われる精神的な嫌がらせが挙げられます。業務に関係のないプライベートについてしつこく詮索するなど、プライベートを攻撃するのもモラハラです。
セクシュアルハラスメント
セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは職場において行われる、性的な言動により、労働者の職場環境が害されたり、労働条件について不利益を受けたりすることです。同性・異性を問わず、被害を受ける側の性的指向や性自認に関わらず、性的な言動であればセクハラに該当します。
たとえば性的な内容の発言をする、デートへしつこく誘う、性的な関係を強要する、身体への不必要な接触などのことです。
セクハラは2種類に分類されます。拒否や抵抗をしたことにより解雇や減給、配置転換といった不利益を受けるのが「対価型セクシュアルハラスメント」。性的な言動により職場の環境が不快なものとなり、従業員が就業する上で支障をきたすのが「環境型セクシュアルハラスメント」です。
出典:「職場のセクシュアルハラスメント妊娠・出産等ハラスメント防止のためのハンドブック」(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000474782.pdf)(厚生労働省)(2024年5月9日に利用)
ジェンダーハラスメント
セクハラと似たものとして挙げられるのがジェンダーハラスメントです。男性だから・女性だからという理由で評価の決めつけを行ったり、「女のくせに」「男のくせに」といった性別による固定観念や差別意識に基づく嫌がらせなどが、ジェンダーハラスメントになります。
男性従業員は名字で呼び、女性従業員は名前や「○○ちゃん」などと呼んで区別することもジェンダーハラスメントの一種です。
マタニティハラスメント/パタニティハラスメント
マタニティハラスメント(マタハラ)は、女性従業員の妊娠・出産が仕事の支障になるとして退職を促したり、妊娠による見た目の変化に対して中傷したりといった行為をすることです。
パタニティハラスメント(パタハラ)のパタニティ(paternity)は「父性」を意味します。男性従業員が育児休業や育児のために時短勤務制度などを活用することに対して、妨害や嫌がらせをする行為がパタハラに該当するのです。
アルコールハラスメント
アルコールハラスメント(アルハラ)とは、アルコール飲料に関する嫌がらせ行為のことです。一気飲みや飲酒の強要、意図的な酔いつぶしや飲めない人への配慮を欠いた、酔った上での迷惑行為などがアルハラに該当します。
一気飲みや飲酒の強要により急性アルコール中毒で緊急搬送される可能性も。最悪の場合死に至ることもあり、アルハラは大きく問題視されています。企業にできる防止策としては従業員全体へ、アルハラに関する教育を行うことや飲み会に関するルール(一気飲み禁止、飲酒を強要しないなど)を定めるといった対応が考えられるでしょう。
近年問題となっているハラスメント
近年「○○ハラスメント」として問題視されているのは上記で紹介したものだけではありません。一例ですが下記のようなハラスメントも存在します。
スモークハラスメント
喫煙者が非喫煙者に対して喫煙を強制したり、たばこの煙にさらされるなどたばこに関する嫌がらせ行為
リストラハラスメント
リストラ対象者に対して嫌がらせ行為を行ったり、不当な配置転換をしたりして労働者を自主退職に追い詰めること
テクノロジーハラスメント
コンピューターやスマートフォン、タブレットなどIT機器の操作に不慣れな人に対する嫌がらせ行為
エイジハラスメント
年齢を強く表現するような呼称を使う、世代でひとくくりにするなど、年齢や世代が違うことを理由にした差別的な言動や嫌がらせ行為
マリッジハラスメント
未婚者へ結婚しない理由を問い詰めたり、結婚しないことを責めたりする嫌がらせ行為
スメルハラスメント
たばこや香水、体臭などのにおいにより周囲を不快にさせる嫌がらせ行為
ソーシャルハラスメント
SNSでのつながりを強要、投稿への干渉、無断で写真を投稿するなどソーシャルネットワークを利用した嫌がらせ行為
いずれにしても行為者のしたことをどう捉えるかは受け手次第です。企業がハラスメントに対しての知識と行動方針を従業員に周知していくことが、ハラスメント防止の第一歩といえるでしょう。
ハラスメントが起こったときの企業リスク
こうしたハラスメントが社内で発生した場合、当人同士だけでなく企業にもさまざまなリスクがもたらされます。
職場環境の悪化
職場でハラスメントが行われていると、従業員の労働に対するモチベーションも下がってしまいます。結果として作業効率が落ちてしまったり、従業員が辞めて人的損失につながったりすることも。ハラスメントは当事者だけでなく、周りの従業員にも影響を及ぼして職場環境が悪化してしまいます。
メンタルヘルス障害による労災認定
ハラスメント被害を受けた人は心の健康を損ない、うつ病などのメンタルヘルス障害を起こしてしまうリスクもあります。「職場でのハラスメントによりメンタルヘルス障害を発症した」として労働災害に認定されるといったケースも。
厚生労働省が出した労災補償状況によれば、仕事が原因で精神障害を発症して労災認定を受けた人は年々増えており、2022年度は710人と前年より81人増加で過去最多に。原因はパワハラが147人で最も多く、ひどい嫌がらせやいじめが73人、セクハラも66人と多数の人が職場のハラスメントにより心を病んでしまっているようです。
出典:「精神障害に関する事案の労災補償状況」(https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/001113802.pdf)(厚生労働省)(2024年5月9日に利用)
企業イメージの低下
「社内でハラスメントが起こっている」という情報は企業イメージの低下にもつながるでしょう。ハラスメントの被害者が裁判を起こしたり、インターネットに企業の評判を書き込んだりすることも考えられます。
また企業イメージが低下すると顧客が離れていく、優秀な人材を採用することが難しくなるなど、取り返しのつかないダメージを負うことになりかねません。
リスクを避けるために事前の防止対策を
社内でハラスメントが起こると被害者個人だけでなく、企業にも大きなリスクが発生するため事前の防止対策が肝要となります。
ハラスメントの加害者は「ハラスメントをしているつもりはなかった」と故意ではないことも多いです。まずはどのような言動がハラスメントに該当するのか、知識や加害者への処分などの方針を従業員全体に周知することが、ハラスメント防止対策への第一歩であるといえます。
企業はハラスメントにどう対応すべき?
防止策をとっていても人間関係が存在する以上、ハラスメントが起こってしまうことは十分に考えられます。そのような場合は迅速かつ慎重な対応が必要です。
初期対応:ハラスメント相談窓口の設置
ハラスメントの知識や処分について周知して従業員への教育をしても、ハラスメントが起こってしまうことはあります。万が一ハラスメントが起こった場合、大切になるのが速やかな初期対応です。
相談者のプライバシーを確保したうえで、迅速かつ適切な対応ができるように、面談だけでなくメールや電話、手紙など相談しやすい環境を整えましょう。受けた相談はプライバシーの保護に注意したうえで記録し、今後の参考になるように管理しておきましょう。この記録は訴訟に発展した際に必要な資料にもなります。
ただし深刻な問題を無理に解決しようするとおおごとになり、かえって相談者を追い込んでしまうことも考えられます。対応範囲を明確にして慎重に対応することも大切です。
行為者への事実確認
被害者からの相談があったら、最初にハラスメント行為者に対して事実確認を行います。
その際に行為者への事情調査を行うことを被害者に伝えますが、被害者が望まない場合は無理に行いません。行為者の監督者(上司など)への観察や指導で対応することもあります。また目撃者や監督者など、どの範囲まで調査を進めてよいかも被害者に確認しておきましょう。
行為者への事実確認の際はプライバシーを厳守することを伝え、以下のようなことを説明します。
- 行為者に対して相談、苦情が入っていること
- 企業として対応するため事実確認を行う必要があること
- 問題解決までの流れ
事実確認として行為者に調査すべき事柄は以下の通りです。
- 相談の対象となっている行為が実際にあったかどうか
- いつどこで、どのような行為であったか
- その行為をした理由
- 相手の反応はどういったものであったか
- 相談者との関係や行為後の関係の変化など
- 目撃者などはいるかどうか
注意点は客観的に事実を把握することです。はじめから加害者と決めつけることなく、中立の立場で話を聞くように努め、弁明の機会を十分に与えるようにしましょう。
また被害者への報復行為や当事者間のみで話し合いを行うことは禁止すると伝えます。相談内容であるハラスメント行為を、被害者へ続けるのも報復行為となることを伝えましょう。企業が責任をもって問題解決にあたるという意思表示を明確にしておくことが必要です。
第三者への事実確認・判断
被害者と行為者の意見が食い違うことも考えられます。その場合、第三者である目撃者や同様の被害を受けた人にも調査をして事実確認を行います。当事者以外の外部にも話が広がりやすくなるため、前述の通り必ず被害者に調査の範囲について了承を得てから調査しましょう。
第三者へは以下のようなことを確認し、職場におけるハラスメントの有無を確認します。
- 見聞きした行為
- 行為者から受けた行為や行為に対する対応
- 相談者から聞いた話
- ほかの目撃者など
当事者(相談者・行為者)の様子や証言内容の矛盾がないかなどに注意しながら、調査結果を分析します。当事者の心理状況に配慮しながら、迅速に公平な判断をする必要があります。場合によっては弁護士や産業医など第三者に意見を求めてもよいでしょう。
調査結果を当事者に伝えて判断に至った経緯や根拠を丁寧に説明し、事実が確認できなかった場合も理由を含めて伝えます。当事者からこの判断について不服申し立てがあった場合は、再度調査を行うことも考えられるでしょう。
ハラスメントの事実が確認できず、相談者から行為者への攻撃を目的とした虚偽の相談であると判断した場合は、虚偽の申し立ては懲戒の対象となる可能性があることを相談者に伝えます。ただしその背景には何らかの原因が潜んでいるもの。その原因を分析することが職場環境の改善にもつながるでしょう。
問題の解決
ハラスメントの事実が確認できた場合、その加害行為をやめさせることや被害者の不利益を回復させること、当事者同士の関係や職場環境の改善を図ります。
たとえば被害者の不当な降給を元に戻す、加害者への指導・研修、加害者の処分、当事者同士を引き離すための配置転換、当事者双方のカウンセリング実施、ハラスメント再発防止に向けた職場環境の整備など、ハラスメント行為の内容と深刻度に応じて解決策を示しましょう。
加害者に関しては行為の内容・程度に対して軽すぎる、あるいは重すぎる処分をしないように公平な判断が必要です。懲戒処分を行う場合はあらかじめ、懲戒事由・種類・程度を就業規則に明記しておく必要があります。
メンタルケアが必要になるのは被害者だけではありません。加害者も心理的ダメージを受けていることがあるため、被害者・加害者の両者にカウンセリングを行うとよいでしょう。
加害者には自身の行為が相手にどう捉えられるのかを理解してもらい、再発防止に努めます。またとくに被害者の心理的ダメージが深刻な場合は、メンタルケアとして医療機関の紹介などを行います。
ハラスメントの問題は解決すれば終わりというものではありません。解決後も当事者双方に定期的なフォローを行い、従業員全体へハラスメントについての知識や方針の教育・研修・周知をしっかりと行っていくことが肝要です。当事者間だけでなく、職場全体で再発防止のための対策に取り組むようにしましょう。
ハラスメントが起こらない働きやすい環境づくりを
ハラスメントは従業員がダメージを負うだけでなく、企業にとっても大きなリスクになります。職場全体の雰囲気が悪化したり、、企業イメージの低下につながることもあるでしょう。
まずはハラスメントに対する従業員の理解不足を解消して防止策をとり、働きやすい環境を整えましょう。もしハラスメントが発生してしまった場合は、迅速かつ慎重に事実確認を行って問題解決を図り、再発防止に努めることが大切です。

