多様性を認め合うことと企業運営は密接に関係しています。ダイバーシティ経営といわれるように、従業員それぞれの能力を最大限に引き出す環境をつくることは企業の重要な課題といえるでしょう。
本記事では、「ダイバーシティ」の基本理解から取り組む効果、企業事例などを解説します。
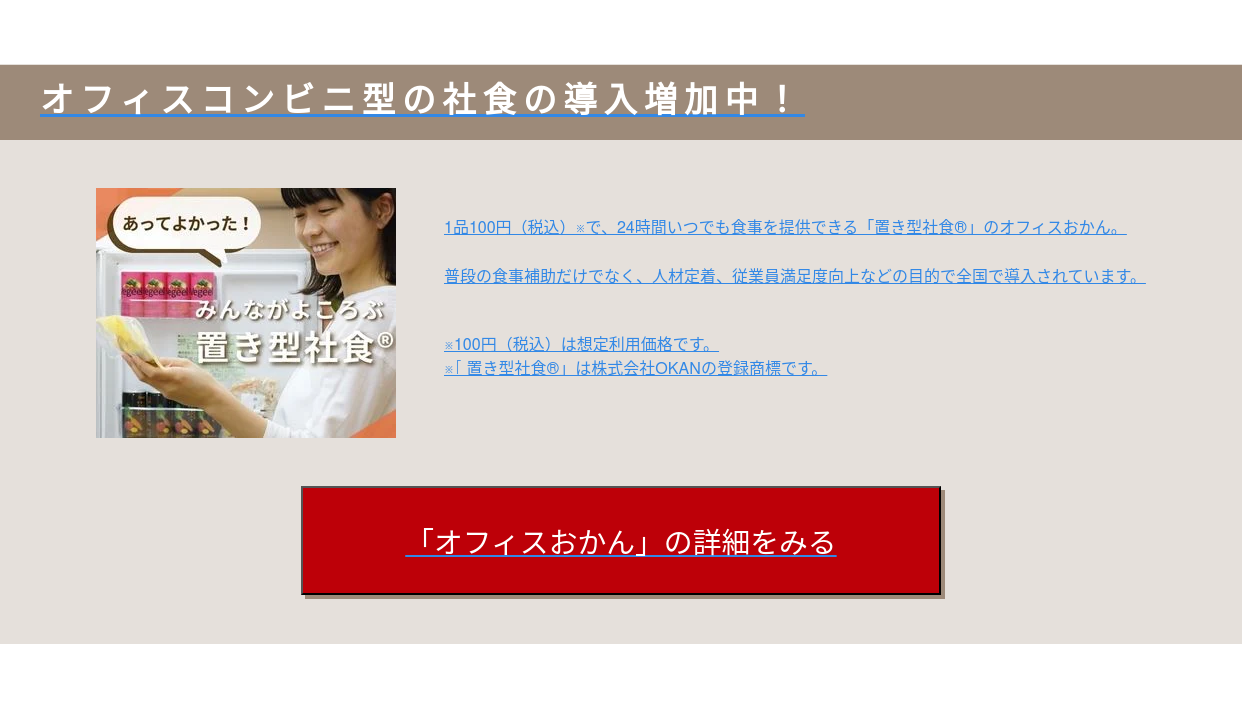
ダイバーシティとは?
ダイバーシティ(Diversity)は「多様性」を意味する名詞で、「Diverse(多種多様)+ity(という性質)」という2つの意味を持つ語で構成されています。
具体的には、「組織や社会の中で、性別や文化、価値観などの違いを尊重し合い受け入れること」を意味しています。ビジネスシーンにおいてダイバーシティを取り入れる目的は、偏った見方や差別などの不公平な意識を持たず、均等で平等に雇用する機会と待遇を提供することにあると言えるでしょう。
2種類に分けられるダイバーシティ
ダイバーシティは、大きく2種類に分けられます。それぞれの特性を解説します。
「表層的ダイバーシティ」とは、人が自分の意思とは関係なく生来持っているものや、自分の力では変えることが難しい属性などを意味します。具体的には、人種、年齢、性別、障害、特性、価値観、性的傾向、民族的な伝統、心理的能力、肉体的能力などが該当します。
「深層的ダイバーシティ」は、人々が内面に持つ大きな違いであり、表面上はわかりにくく、違いに気づきにくいものを指します。具体的には、宗教、母国語、職務経験、収入、働き方、学歴、コミュニケーション特性、組織での役職などが該当します。
2種類のダイバーシティには、企業の採用やマネジメントの取り組みやすさにも違いがあります。外から見てわかりやすい「表層的ダイバーシティ」は、企業に取り入れやすく、はじめてのダイバーシティ経営でも取り組みやすいでしょう。
「深層的ダイバーシティ」は、それぞれが違った職務経験や働き方など、多様性が増すことで新しい価値観が業績アップにつながる可能性も期待できます。
ダイバーシティ経営(マネジメント)とは?
ダイバーシティ経営とは、多様な人材の能力を最大限に活かすことで、企業の競争力が強化され、事業が成長していくという考え方です。女性、外国人、高齢者、障がい者を含めたさまざまな人材が活躍できるよう、経営戦略的に組織を管理していくことで「革新」や「新機軸」を意味するイノベーションへとつながります。
出典:「ダイバーシティ経営の推進」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/)(2024年5月19日に利用)
また、イノベーションに関連してダイバーシティマネジメントという手法も存在します。企業として多様な人材のアイデアやスキルを活かしていくために、どうマネジメントしていくかが、ますます重要になるでしょう。
アメリカでは、ダイバーシティマネジメントを「多様性の受容」を意味するダイバーシティ&インクルージョンと表記しており、同様の表現をする日本企業もあります。
また、昨今ではワークライフバランスを重視する働き方が浸透する中、企業側でも多様化する雇用意識や価値観へ対応した柔軟なマネジメントを行うことが必要です。従業員それぞれの能力が発揮される企業文化の構築が求められています。
ジェンダー・ダイバーシティ・マネジメント
さまざまなダイバーシティ・マネジメントの中でも、女性の積極的な管理職登用を意識したものがジェンダー・ダイバーシティ・マネジメントです。たとえば、マネジメントや公正な評価・処遇、目標管理などの施策に取り組むことなどを指します。
ジェンダー・ダイバーシティ・マネジメントとワーク・ライフ・バランスを併用するとさらに女性の活躍が期待できるでしょう。
ダイバーシティが必要とされる背景
企業でもダイバーシティが重視されるようになった理由は複数あります。
働き方に対する価値観の多様化
時代とともに、働き方や雇用に対する意識は大きく変化しました。
価値観が多様化する流れの中で女性の雇用比率が高まったことにより、家事・育児に対する男性の役割も変化しました。今までの時代の流れと比べると家事・育児に積極的に関わる男性が増える傾向にあり、男性・女性に関係なく自分らしく楽しみながら行うことが浸透してきています。
企業としても、ダイバーシティを実践することで、世の中の働き方に対する価値観の変化に対応していく必要があります。
ビジネスのグローバル化
グローバル化とは、国や地域を超えて事業活動の中で海外とのやりとりが行われることを指します。日本でも近年、ビジネスのグローバル化が急速に進んでいます。
海外市場のニーズに合う商品開発を行ったり、海外拠点をつくったりするために、企業ではさまざまな国籍や人種の人材採用を必要としています。多様な価値観を受容していくダイバーシティを推進することで、外国籍の方でも働きやすくなるでしょう。
少子化高齢化などによる労働力人口の減少
15歳から64歳までの社会で働く年齢に適している人たちのことを「生産年齢人口」と称します。少子高齢化に伴い、生産年齢人口は年々減少傾向にあります。その結果、今後の日本では深刻な人手不足に陥ると懸念されています。人手不足により事業が継続できなくなることも懸念されるため、安定した事業の継続のためには従業員を安定して確保する必要があります。
そこで、ダイバーシティの考え方に基づき、女性や高齢者、障がい者、外国人などの多様な人材を活用することが重要とされています。
フルコミットメント社員の減少
フルコミットメント社員とは、一般的に「どんな状況でも責任を持って全力で業務に取り組む社員」を指します。生産年齢人口の減少に加え、高齢化により要介護者数および介護に従事する人口も増加している背景から、フルコミットメント社員を確保することが以前よりも難しくなり、人材不足が懸念されるようになりました。
出典:「介護分野をめぐる状況について」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000608284.pdf)(2024年5月24日に利用)
企業はダイバーシティを進め、フルコミットメントではない時短労働者やリモートワーカーなど労働力の活用が求められるようになっています。
顧客の価値観の多様化
日本の消費者の消費志向は、市場の成熟を経て多様化しています。消費行動は「モノ消費」から体験を買うという「コト消費」が重視される傾向にあります。
そのような消費行動の多様化に対応していく企業戦略を立てるためにも、多様な人材を受け入れ、柔軟性と創造性のある組織づくりを推進していく必要があるでしょう。
ダイバーシティ推進で得られる4つの効果
企業がダイバーシティを推進することで、どのような効果を得られるのでしょうか。
プロセスイノベーション
プロセスイノベーションとは、製品やサービスの開発・製造・販売の過程、つまり「プロセス」を改良することを指します。ダイバーシティによって多様な人材が企業内にいることで、効率化のアイデアや販売手法の改善案が浮かびやすくなります。
プロダクトイノベーション
プロダクトイノベーションとは、製品やサービスの新しい価値を生み出したり、改良や開発を行ったりすることです。多様な価値観を持つ人材が集まることで、従来とは違った視点で製品・サービス企画が生まれる事例が期待されます。
たとえば、日本人のみの企業に海外出身の人材が入社することで、海外市場に適した商品企画ができるようになり、海外商品のアイデアを取り込むことが可能になります。
外部からの評価の向上
多様な価値観を大事にした働き方を推進することで、企業の社会的な評価が高まります。自社の従業員を大事にしているという印象を持たれるため、採用力の向上が期待できます。
また、多様な人材を採用してユーザーニーズを汲み取った事業を行えば、顧客からの信頼も高まるでしょう。結果として顧客満足度が上昇し、企業のブランド力向上に効果的です。
職場内の効果
フレックス制度や時短勤務、リモートワークなど、さまざまな働き方が可能となることで、従業員が自身の都合に合わせた勤務を続けられます。従業員のモチベーションアップや心身の健康向上に役立ち、離職率の低下も見込めるでしょう。
ダイバーシティを推進するための5つのポイント
ダイバーシティを推進し、企業文化として定着させるためにおさえておきたい5つのポイントを解説します。
意思決定の透明性
企業に多様な人材を集め、それぞれが活躍できる環境にするためには、業務における意志決定の透明性が高くなければなりません。さまざまな価値観を持つ人を受け入れるダイバーシティ経営においては、「空気を読む」や「言わなくても察する」という日本人にありがちな意識は、かえってトラブルを招く可能性があります。
意思決定のプロセスが透明化されることで、従業員の企業に対する信頼感が増し、意見が出しやすい場所となるでしょう。
一人ひとりの意見を尊重する
ダイバーシティ経営推進のためには、従業員がさまざまな意見を出せる環境づくりと、意見を尊重し採用することが重要です。
自己主張が得意でないタイプの従業員にも、意見を出しやすい環境をつくることも大切です。気軽に使える相談フォームやチャットツール、意見箱などでアイデアを簡単に持ちこめる場をつくるなどの工夫が必要でしょう。
属性で人を見ず、「個」を見る
プロジェクトを立ち上げる際には、属性で人を見ず、個々をしっかりと見極めることが大切です。
たとえば、若年層向けの商品を開発する場合、若年社員だけのチームをつくって丸投げすればよいというわけではありません。「若年層」と、ひとくくりにされることでアイデアが限定されてしまう可能性があります。違う世代の従業員からのアイデアが、商品の開発する上で、良い足掛かりになることもあるでしょう。
「女性」や「若年層」「外国人」という属性の集団で従業員を見ず、それぞれ個人として捉えた上で思想や得意・不得意などを把握しておくことが重要です。
縦割り組織を防ぐコミュニケーションの工夫
ダイバーシティ・マネジメントの推進と浸透に不可欠なことは、円滑なコミュニケーションです。
組織が硬直化していたり、縦割りだったりすると、従業員同士のコミュニケーションが分断されてしまいます。円滑な情報共有や意見発信が困難になることを防ぐためには、コミュニケーションの工夫が必要でしょう。
組織を横断して行うプロジェクトや、役職や肩書きを気にせずに意見交換ができるオフサイトミーティングを取り入れることで、組織内のコミュニケーションが円滑に行えるようになるでしょう。
社内での発信・共有
ダイバーシティの取り組みはやりっぱなしにせず、経営層が成果へのフィードバックを従業員向けに行うとよいでしょう。
成果を従業員と共有することで、より良い循環が生まれやすくなります。社内への積極的な情報発信として、表彰や社内広報システムを利用した共有を行うと効果的でしょう。
ダイバーシティ疲れに注意
ダイバーシティ経営に取り組んでもなかなか成果が現れない場合、企業担当者の「ダイバーシティ疲れ」に注意が必要です。
「女性を管理職に登用したのに妊娠・出産で退職してしまった」「制度を用意しても、結局辞められてしまう」という企業側の意識と、「本当は働きたいのに、辞めざるを得ない状況に陥っている」という女性側の意識にズレが生じてしまう可能性もあります。
実際に女性が活躍できる「ジェンダー・ダイバーシティ経営」を叶えるためには、企業の取り入れた制度や取り組みが、本当に女性の役に立っているかどうかの判断が重要です。
ダイバーシティ経営を成功に導くには、多様な価値観を持つ人材を受容する必要があります。管理職側が従業員の能力を汲み取り、活躍に導くスキルを意識して身につけましょう。また、従業員と経営層がこまめにコミュニケーションを取りながら、自分らしく働けるような社内の制度づくりやサポート体制の構築を行うことが大切です。
企業でダイバーシティを推進するための4つの施策
ダイバーシティ経営を推進するには、どのような施策を行うのが効果的か4つの施策について具体的に解説します。
柔軟なワークスタイルを整備する
柔軟なワークスタイルで働けることは、従業員のワークライフバランスを充実させるためにも一役買います。
育児休業や介護休業などの制度は、整備するだけでなく、活用しやすい状態になっていることが大事です。相談窓口を設置したり、休業後の復職支援システムを設けたりなど、従業員が働きやすい環境をつくるための工夫が必要でしょう。
また、裁量労働制やフレックスタイム制などといった柔軟な勤務体系を取り入れることで、ワークライフバランスを重視する人や、介護中や育児中の人たちにアプローチできます。
さらに、リモートワークを導入したり、サテライトオフィスをつくることで、従業員の働く場所が柔軟になります。通勤電車から解放され、オフィスへのアクセスにとらわれず住む場所を選択できることは、従業員の心身の健康に好影響をもたらすでしょう。
働きやすい雰囲気づくりを心がける
役員の中にダイバーシティ担当者を設定し、専用の相談窓口を設けることで相談しやすい環境づくりが可能です。些細なことでも相談できる働きやすい雰囲気をつくることで、マイノリティや困りごとを抱えた人が孤立しにくくなるでしょう。
経営層への研修の実施
研修は、従業員だけではなく経営層を含めた実施が不可欠です。ダイバーシティをただの一時的な取り組みではなく、企業文化と言えるほど浸透させることが効果的でしょう。
研修では、女性やLGBT、高齢者や障がい者、介護従事者など、それぞれに対して自分たちがどのような認識の歪みや偏りを持っており、どのようにして取り除けばよいのかを学びます。経営層が学んだことを積極的に経営方針に取り入れることで、ダイバーシティが強力に進んでいくでしょう。
成長機会の提供
従業員が興味のあるプロジェクトに携われる機会を得られやすいような仕組みも、モチベーションアップに有効です。ただし、雇用形態に関わらず機会を公平に提供することが重要になります。
また、キャリア形成支援研修を実施したり、メンター制度を取り入れたりなど、成長できる機会を誰でも得られるようにすることも大切です。成長するチャンスを明確にすることで、自社でキャリア形成をする意識が高まるでしょう。
ダイバーシティ施策の事例
ダイバーシティ経営の推進企業として、経済産業大臣表彰となる「令和2年度新・ダイバーシティ経営企業100選」から抜粋して紹介します。
個の多様性を高めるキャリア構築や管理職の意識改革など|BIPROGY株式会社(旧:日本ユニシス株式会社)
BIPROGY(旧:日本ユニシス)では、個の多様性を高め、チャレンジする組織風土の醸造に向けた仕組みを提供しています。キャリア相談窓口や「e-キャリアボード」で自律的なキャリア構築を支援しているのが特徴です。
そのほか、管理職による研修の実施やコーチングプログラムの導入など、ダイバーシティ推進となる行動変容に働きかけるための行動と意識改革に取り組んでいます。
出典:「令和2年度 新・ダイバーシティ経営企業100選 100選プライム/新100選ベストプラクティス集(日本ユニシス株式会社)」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/r2besupura.pdf)(2024年5月17日に利用)
服装自由化、性別を問わない育児休業の取得など|カンロ株式会社
カンロ株式会社では、以下のような働きやすい環境づくりを行っています。
- 家庭と仕事の両立支援および働く場所と時間の選択の多様化
- フレックスタイム制度のコアタイム短縮・服装自由化
- 性別を問わない育児休業の取得
働き方改革などの取り組みの結果として、男性の育児休業取得率は上昇し、職場環境の良さや働きやすさから優秀なキャリア社員の獲得にも成功しています。また、経営層は女性監査役1名、女性執行役員1名が在住するなど、女性マネージャーを起用し、主力ブランドの育成にも取り組んでいます。
出典:「令和2年度 新・ダイバーシティ経営企業100選 100選プライム/新100選ベストプラクティス集(カンロ株式会社)」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/r2besupura.pdf)(2024年5月17日に利用)
イクボス研修やダイバーシティ研修を実施|エーザイ株式会社
エーザイ株式会社では、管理職に対してイクボス(部下や同僚の育児や介護などに配慮・理解がある上司)に関する研修や、新任組織長にダイバーシティ研修を行うなど企業成長に活かせる組織風土を醸成するための意識改革に取り組んでいます。
また、企業全体でグローバル人材の育成にも積極的です。「グローバルモビリティプログラム」による国を超えた派遣を経験し、グローバルビジネスをリードする人材へと成長させています。
ダイバーシティ経営による、多様な人材のキャリアアップと女性の管理職比率の更なる上昇が今後の目標です。
出典:「令和2年度 新・ダイバーシティ経営企業100選 100選プライム/新100選ベストプラクティス集(エーザイ株式会社)」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/r2besupura.pdf)(2024年5月17日に利用)
管理職向けの「イクボス養成講座」を実施|四国銀行
四国銀行では、将来を担う人材の育成と開発、女性社員の活躍機会の拡大、組織活力の向上に取り組んでいます。そのほか、育児による短時間勤務制度の利用要件を「小学校就学まで」から「小学3年生修了まで」に期間を拡大するなど、女性が働きやすい環境づくりを積極的に行っています。
また、職場の部下やスタッフのワークライフバランスを考えながら、新任管理職と係長級クラスに「イクボス養成講座」を実施するなど、経営者や管理職への研修・啓蒙にも努めています。
出典:「令和2年度 新・ダイバーシティ経営企業100選 100選プライム/新100選ベストプラクティス集(四国銀行)」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/r2besupura.pdf)(2024年5月17日に利用)
看護休暇や介護休暇を有給化|株式会社ズコーシャ
株式会社ズコーシャでは、以下のようなワークライフバランスに考慮した働き方改革を推進し、性別や年齢等を問わず全ての社員がライフステージにあわせて多様かつ継続的に働ける環境を整えています。
- フレックスタイム制の導入
- 子の看護休暇や介護休暇の有給化
多様なキャリアを有する人材が能力を最大限に発揮し、イノベーションを生み出しながら、企業価値の創造につなげていることが評価されています。
出典:「令和2年度 新・ダイバーシティ経営企業100選 100選プライム/新100選ベストプラクティス集(株式会社ズコーシャ)」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/r2besupura.pdf)(2024年5月17日に利用)
真の「多様性」実現のために企業がすべきことを考えよう!
ダイバーシティ経営を実現し、企業内に浸透させるのは簡単なことではありません。
経営層、マネージャー層と従業員が密にコミュニケーションを取り、表面的ではなく、真の「多様性」を受容した働き方や採用スタイルの整備を、長い目で見ながら行う必要があるでしょう。
すでに取り組みを続けて成果をあげている他社の事例などを見ながら、自社に取り入れたいダイバーシティ経営のあり方を考えてみてはいかがでしょうか。

