企業は人で成り立っており、社員なしで会社を運営することはできません。そのため、人材教育は、企業の成長にとって必要不可欠です。最近では、人材に対して積極的に資源投入をする会社が増えてきました。
教育に力を入れれば従業員も自分の成長を感じることができ、働きがい向上につながります。社員教育をおこなうことで、社員が働きがいを感じられ、会社も成長するといった好循環を回していくことがとても大切です。
この記事では社員教育の種類や運営目的、計画の仕方などを詳しく解説していきます。「人材教育にこれからさらに力を入れたい」という人事担当者の方はぜひ参考にしてみてください。
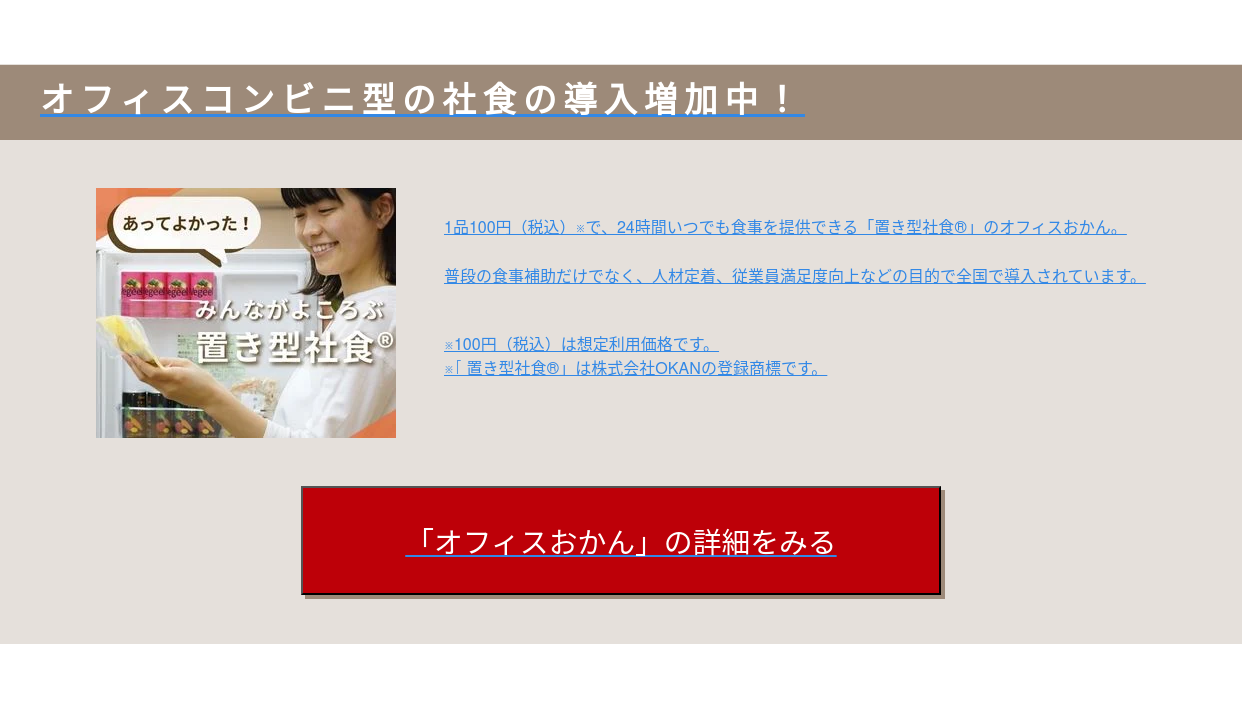
社員教育の種類|人材教育はさまざまな場面でおこなわれる
社員教育は実施するタイミングや対象者によって、内容が大きく異なります。それぞれの研修でおこなうべきことを把握し、効果的な教育プログラムを実施しましょう。
内定者研修・新入社員研修
内定者研修・新人社員研修は、文字通り内定者や新入社員に対しておこなわれる研修です。多くの場合、ビジネスマナーや社会人としての基礎知識などを学ぶ場として設けられます。入社前の内定段階から会社との接点を多く持たせることで、内定辞退を防止する目的もあります。
内定者研修・新人社員研修をおこなう際は即戦力を養うための短期的視点だけでなく、長期的な視野を持つことが重要です。「将来的にどういうキャリア形成をしていきたいのか」「入社して何を成し遂げたいのか」を社員に考えさせましょう。単に知識を学ぶだけの研修ではなく、内容に厚みを持たせることが必要です。
若手・中堅社員研修
若手・中堅社員研修は、入社3〜10年ごろにおこなわれる研修を指します。入社して数年(入社3〜5年)は、仕事にも慣れ、ひとりでおおよそのことができるようになる時期です。
若手社員の成長を促すとともに、優秀な人材を外に逃さないために若手社員研修は大切であるといえます。中堅は後輩が増えてきて、小さいチームをまとめる役割を担い始める年代です。研修を通じて次のステップを見せることは、社員のモチベーション維持にもつながります。
役職者向け研修
課長職や部長職向けにおこなわれる研修では、より高度な内容が求められます。役職者は現場のマネジメント力と同時に、組織横断的・全社的な視点で物事を考える力を養う必要があります。
管理職に求められる最も重要なことは、「チーム力を最大化させること」です。そのためには、部下一人ひとりの特性を活かすチームづくりが必要です。プレイヤーとしての立場からステップアップし、マネージャーとしての力を養うための研修を実施しましょう。
社員教育の方法|大きくOJTとOFF-JTに分けられる
社員教育の手法は、大きく分けると「OJT」と「OFF-JT」の2種類があります。どちらかに偏ることなく、同時にバランスよく実施することが大切です。
OJT
OJTとは「On The Job Training」の頭文字をとった言葉で、日常業務のなかでおこなうトレーニングのことを指します。実践の中で学んでいくため、力が身につきやすい点がメリットです。
日々の業務に忙殺され、「部下の教育に手が回らない」という職場も少なくありません。OJTを効果的に実施するためには、職場全体の意識付けも大切です。
OFF-JT
OJTに対してOFF-JTは、職場とは別の場所でおこなわれる教育のことです。実践力を養うよりは、理論や知識を学ぶ場として開かれるのが一般的です。OFF-JTの形態は「グループ研修」「eラーニング」「個別研修・自習」などのスタイルに分けられます。
グループ研修は複数の社員が参加するため、社員交流の場にもなりえます。互いを尊重しながら意見交換をおこなえるため、社内のコミュニケーション活性化につながります。一方で、時間とコストがかかる点はデメリットです。
eラーニングは近年導入する企業が多い研修形態で、インターネットを使って実施します。グループ研修よりもコストが抑えられ、各社員の都合のいいタイミングでの受講が可能です。
eラーニングの研修内容は非常に多様化してきています。ビジネスマナーやマネジメントのような基本的な内容から、語学・プログラミング・デザインなどの専門分野までさまざまなものが存在します。
社員教育において重要なのは、「OJTとOFF-JTをうまく組み合わせて社員の成長を促すこと」です。OFF-JTで学んだ知識や理論をOJTで実践していくサイクルを円滑に回すことが大切です。
社員教育プログラムを考える
![]()
次に、実際に社員教育のプログラムを構築するプロセスを見ていきましょう。
社員教育をおこなう意義・目的を明確にする
社員教育や人材教育のカリキュラム作りに着手する場合、まずは目的をはっきりとさせる必要があります。目的が不明確なまま始めてしまうと、「せっかく研修をやったけど何も身につかなかった」という事態になりかねません。
社員教育の目的は会社によってさまざまですが、主な方向性は以下の3つです。
- 社会人としての基礎を養う:ビジネスマナーや社会規範、コミュニケーション能力など
- より高次のスキルを身につける:語学、マネジメントスキル、経営学、リーダーシップなど
- 社内の文化を醸成する:コーポレートミッションの浸透、コンプライアンス意識の構築など
1つ目と2つ目は、さまざまな企業で実施されている一般的な研修内容です。意外と見落としがちなのが3つ目の「社内文化の醸成」です。文化は長い間かけて作りあげていくものであるため、取り組みをおこなってすぐに効果が出るものではありません。定量的に評価しづらく費用対効果が見えないため、ないがしろにされやすい分野です。
しかし、会社を長く存続させていくためには、長期的な視点が不可欠です。「5年後、10年後に会社がどうなっているか」という観点も持ちながら、社員教育プログラムを考えていきましょう。
社員教育の期間・カリキュラムなどを定める
教育の目的を明確にしたら、次にプログラムの内容を考えます。ここでは内容を構築するプロセスの例として、新入社員研修について考えてみましょう。「社会人としての基本的なスキルの体得」と「5年後の自分のイメージを持たせること」を教育の目的に設定した場合で考えます。
研修内容の構築は、以下のような手順で進めます。
1. 目的を明確にする
2. 研修後の姿を描く
3. 「研修後の姿」と「現状」のギャップを把握する
4. それを埋めるために必要なことを挙げる
5. カリキュラムに落とし込む
6. 効果測定をする
7. アフターフォローの仕組みを考える
このプロセスでは、「PDCAサイクル」を実践しています。PDCAサイクルとは、計画、実行、評価、改善のサイクルを指します。つまり、研修をして終わりではなく、計画から実行、アフターフォローまでをしっかりと考えてデザインすることが重要です。
社員教育をおこなう上での注意点
ここでは、社員教育のプログラムを考えるうえで気をつけるべきことをご説明します。
参加者に研修目的を理解させる
社員教育・研修の目的を明確にすることはとても重要です。人事部などの企画側だけでなく、参加者にも目的の周知徹底を心がけましょう。
実務につながる内容にする
OFF-JTを座学でおこなう場合、できるかぎり実践につながる設計にしましょう。研修内容があまりにも現場の実態とかい離していると、研修自体が形骸化してしまう恐れがあります。
能動的に学べる雰囲気づくり、仕組みづくりをする
「会議や研修の場で活発な発言がおこなわれない」との悩みを抱える人事担当者は少なくありません。講師や一部の参加者が一方的にしゃべるのではなく、みんなが発言・参加しやすい雰囲気をつくるようにしましょう。
研修後のフォローアップも怠らない
研修実施後のアフターフォローも忘れてはいけません。社員教育は、学んだ内容を仕事で活かさなければ意味がありません。「研修での気づきを自部署で発表する」「研修内容を上司と共有する」などのフォローをおこなうようにしましょう。
社員教育・人材教育制度が充実してる企業
ここでは、実際におこなわれている社員教育の実例を見ていきましょう。注目すべき点として、紹介する企業はどこも教育をおこなう意義が明確です。ぜひ参考にしてみてください。
株式会社ネットサポート
株式会社ネットサポートは、サーバーやネットワークシステムの設計・運営をおこなう会社です。ITエンジニアが多く在籍しており、IT業界未経験者でも働ける研修体制がしっかりとしています。社会人としての基本スキルにくわえ、プログラミングやネットワークについての講義もおこなわれます。
【人材教育の特徴】
- 「社員の成長が会社の成長」という考えを持つ会社
- エンジニアを育てる素養がある
株式会社ネットサポートでは、新人社員に対するフォローアップ体制が整っており、社員が成長し続けられるような環境づくりがされています。
(参照:株式会社ネットサポート「育成・研修体制(https://www.n-support.jp/recruit/about/education.html)」『NET SUPPORT RECRUTING SITE』、参照日:2024/05/14)
株式会社日本SPセンター
株式会社日本SPセンターの特徴は、年間100以上もの社内講義を実施している点です。社内講義の内容は営業から企画、デザイン、マーケティングなどさまざまで、講師はすべて現役社員が担当します。現場で使える、実践的なスキルや考え方を習得できる体制づくりがされています。社内勉強会や発表会も盛んで、社員同士で切磋琢磨する風土が根付いている会社です。
【人材教育の特徴】
- 年間100以上もの講義が実施される
- 社内勉強会や定例行事が盛ん
(参照:株式会社日本SPセンター「社内研修(https://nspc.co.jp/recruit/support/)」『日本SPセンター』、参照日:2024/05/14)
株式会社シンクアクト
株式会社シンクアクトは、ネイルサロンの運営を手掛ける会社です。同社では、ネイル技術と接客に関する研修が2カ月間おこなわれます。9割以上の社員が未経験からスタートし、プロネイリストとして活躍しています。
【人材教育の特徴】
- スチューデントサロンによる実践研修
- OFF-JTプログラムが充実している
(参照:株式会社シンクアクト「未経験という『不安』から、できるんだという『自信』へ(https://nonail-tokyo.com/recruit)」『No Nail NAIL SALON』、参照日:2024/05/14)
リソース不足ならアウトソース|おすすめのeラーニングサービス
「社内にノウハウがない」「人事担当者が少なく、社員教育に手が回らない」などでお困りの場合には、外注サービスを利用するのもひとつの手です。特にeラーニングは比較的安価で、少人数からでも導入できるのでおすすめです。
ネットラーニング
ネットラーニングはeラーニングの最大手サービスです。加入している法人数は6000社を超え、講座の数は1万コース以上に及びます。講座の種類の例を挙げると、DX人材育成やIT系情報技術、ビジネススキルや語学などさまざまです。全社員向けの講座から、新人若手向け、マネジメント層向けなど企業の幅広いニーズに応えます。
研修運営や受講者のフォローまで行う学習支援サービスもネットラーニングの特徴です。
(参照:株式会社ネットラーニング「ネットラーニングが選ばれる理由(https://www.netlearning.co.jp/)」『Net Learning』、参照日:2024/05/14)
Udemy
Udemyは世界中で利用されているオンライン教育プラットフォームです。アメリカ企業発のサービスですが、日本ではベネッセが事業パートナーとして運営を担っています。Udemyは特にIT系の講座が強く、実務に直結するスキルを学ぶことができます。
(参照:株式会社ベネッセコーポレーション「実践的かつ最先端の知見が学べる「
Udemy Business』(https://ufb.benesse.co.jp/)」『Udemy Business』、参照日:2024/05/14)
社員教育で優秀な人材の離職防止へ
人材教育は、企業の成長において重要な要素であり、企業は人により成り立っており、持続的に成長していくためには社員教育は必要不可欠です。
教育に力を入れれば、社員の働きがいにもつながります。人手不足が叫ばれる日本において社員教育に注力することは、優秀な人材の流出を防ぐためにも重要な取り組みといえるでしょう。是非この記事を参考にして、人材教育を行う上での参考にしてください。

