家族がいる従業員に対して支給される家族手当。時代の流れから、制度の廃止を検討する企業もあるようです。そもそも、家族手当とはどういう制度で、どのような条件のときに支給するものなのでしょうか。制度の基本的な事項から、現在どのような代替制度へ移り変わっているかを解説します。
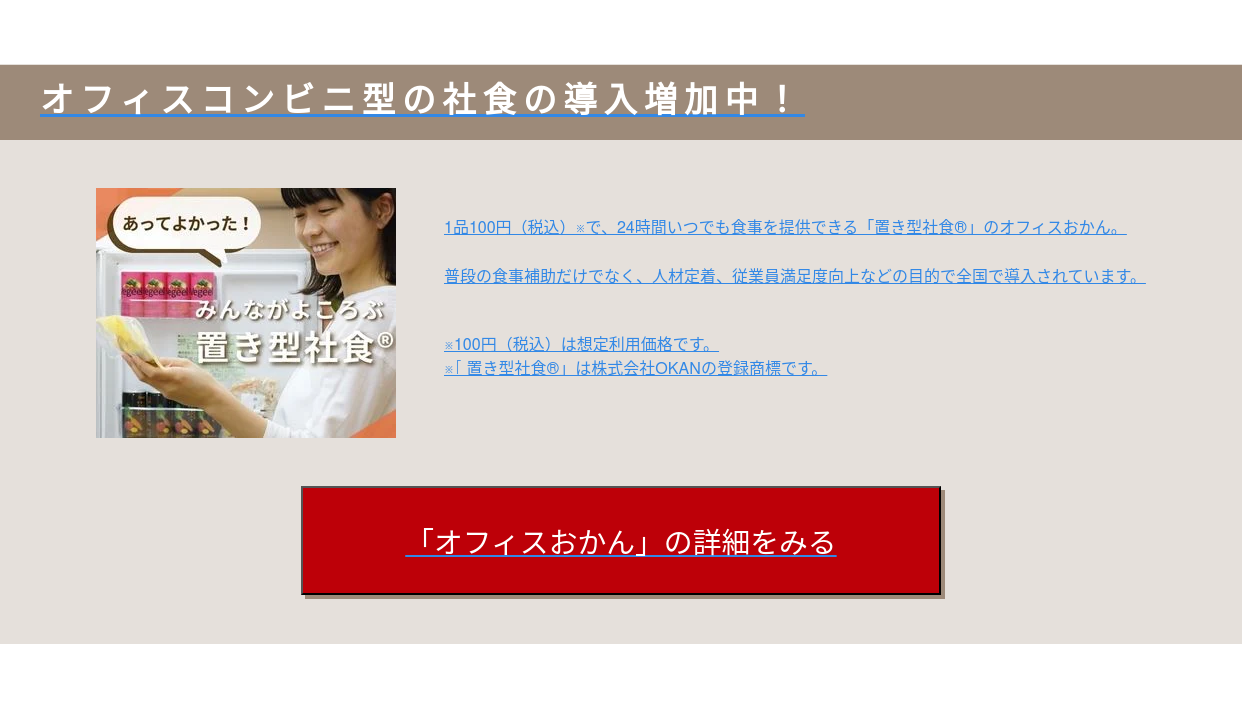
家族手当とは何か
家族手当とは、配偶者や子どもなどといった家族を養っている従業員に対し、扶養される家族1人あたりの年収が103万円未満などといった一定の条件を満たしていれば、基本給とは別途で支給される手当のことです。対象は、配偶者や子どもなどを抱える従業員であり、世帯の経済的負担を軽くする目的として設けられた制度でもあります。
また、企業によっては名称の呼び名が異なっており、「扶養手当」として運用している場合もあれば、さらに細分化して配偶者を対象とした「配偶者手当」、子どものみを対象とした「子ども手当」などという名称で対応している例もあります。
家族手当の支給については、法定外福利厚生の扱いとなるため、企業側の支給義務を設けていません。そのため、企業によっては家族手当、もしくは家族手当と類似の手当を支給していないという場合もあります。
近年では、家族手当を廃止、もしくは見直す企業も出てきており、18歳未満の子どもがいる世帯や要介護の親族がいる世帯に絞って支給をするというケースもあるそうです。
出典:「「配偶者手当」の在り方の 検討に向けて」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001040024.pdf)(2024年4月22日に利用)
出典:「配偶者を対象とした手当に関する見直しが実施・検討された事例等」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000123734.pdf)(2024年4月22日に利用)
家族手当の現状
現在、家族手当は一般的にどれくらいの金額が支給され、どれくらいの割合の企業が支給をしているのでしょうか。
いくら支給されているか
法定外福利厚生である家族手当は、企業によって制度の有無や金額が異なっているので、基準額や決められた金額はありません。東京都産業労働局が発表した『中小企業の賃金・退職金事情(令和5年版)』によると、家族手当平均額は8,798円でした。
ちなみに業界別だと製造業の平均が8,400円、卸売業・小売業の平均が10,788円です。こちらの金額は東京都で調査した結果なので、全国平均ではありませんが、「家族手当がどのくらい支給されているか」という観点では参考情報になるでしょう。
出典:「「配偶者手当」の在り方の 検討に向けて」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001040024.pdf)(2024年4月22日に利用)
出典:「配偶者を対象とした手当に関する見直しが実施・検討された事例等」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000123734.pdf)(2024年4月22日に利用)
(参照:東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和5年版)(https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/koyou/r5chintyo_zenbun.pdf)」、参照日:2024/02/24、調査主体:東京都、調査対象:従業員10人から299人の都内中小企業を対象に876社に実施した調査、単一回答、集計集計期間:2023年7月。)
家族手当が支給されている企業の割合
人事院が公表している『令和5年職種別民間給与実態調査』によると、家族手当制度を導入している企業の割合は全体で75.5%です。
下記の表では企業の規模別にまとめた数値を示していますが、7割程度の企業が家族手当を取り入れていることがわかります。特に規模が大きな企業の方が家族手当が支給されている割合が高いということも把握できるでしょう。
家族手当支給状況
| |
支給企業割合(%) |
| 500人以上 |
76.3 |
| 100~499人 |
75.2 |
| 50~99299人 |
68.6 |
出典:「民間給与の実態 (令和5年職種別民間給与実態調査の結果)」(人事院)(https://www.jinji.go.jp/kyuuyo/kouho_houdo/toukei/minn/minnhp/minR05_index.html)(2024年4月23日利用)(調査主体:人事院、調査対象:企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の全国の民間事業所、単一回答、集計計測期間:2023年4月24日から6月16日の期間。)
家族手当の支給条件とは
家族手当の支給対象となる範囲
「家族手当」とされた場合、支給対象となる家族は「配偶者」「子ども」「両親」のいずれか、または全てを含む場合があり、企業によっても対象が異なります。
しかしながら、これらの範囲に含まれていても、無条件に支給対象となるわけではありません。対象となる家族の収入や子どもの年齢や人数といった世帯状況で手当の対象になるかならないかの判断がなされます。
出典:「配偶者を対象とした手当に関する見直しが実施・検討された事例等」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000123734.pdf)(2024年4月23日に利用)
支給対象となる家族の年齢条件
対象家族を年齢で限定する場合、子どもは「18歳未満」など年齢を定め、両親は「満60歳以上」というように就業中の年齢を除外して定める例もあるそうです。
支給対象となる家族の収入制限
収入の上限としては、「所得税の配偶者控除が受けられる年収103万円以下」または「社会保険の被扶養者として認められる年収130万円未満」を基準とする企業も存在するそうです。
支給対象となる家族と同居しているか
「対象となる家族が従業員と同居しているかどうか」「対象となる家族が従業員の同一生計内で生活しているかどうか」という規定を設けている企業もあります。「同居」が条件である場合は、子や配偶者であっても別居している時点で支給対象からは外れます。
ただし、大学生の子どもが実家を出て一人暮らしをしている場合や単身赴任で配偶者や子どもと別居している場合、別居をしている両親がいる場合などであっても、扶養者である者が生活費を送っているのであれば「同一生計内」と見なされるので、同一生計であることが条件という場合は支給対象となる可能性があるでしょう。
また配偶者の定義を「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む」や「戸籍上の性別を問わない」のようにしている場合、事実婚や、同性のパートナーであったとしても、他の条件を満たせば支給対象となる場合もあります。
家族の形も多様化している今、このようなケースも発生するかもしれないので、社内の家族手当の定義を明確にしておくと良いでしょう。
家族手当を支給することによる影響
家族手当は、家族を抱える従業員にとっては何かと助かりますが、実際のところ、企業にとって、そして従業員にとってどのような影響が生じているのでしょうか。
支給するメリット
家族手当を支給することは、家族を抱える従業員にとって経済的な支援となり、家計の負担を軽減する助けになるでしょう。
手当を支給することで、従業員の満足度が上がり、離職率が下がるとも言われています。また、家族手当は、すでに働いている従業員だけでなく、求職者にとって転職先を選ぶ条件として魅力的な要素とも言われており、企業としての価値を上げられる見込みがあるでしょう。
企業にとっては、従業員のモチベーションを高め、長期的には離職率を減少させる効果もあります。ただし、家族構成によって手当が異なるため、単身者など他の従業員との間で不公平感が生じるリスクも考慮する必要があります。このように、家族手当は多くのメリットを提供しながら、適切な管理とバランスが求められる制度です。
支給するデメリット
家族手当の支給にはデメリットも存在します。その中でも特に対象外の単身者や子どもがいない従業員から、「不公平」という声が上がる場合があり、誰もが満足できる手当とは言い難いでしょう。企業によっては、従業員の公平さを優先した形で家族手当を廃止しているというケースもあります。
また、扶養する家族の人数が多ければ多いほど、企業が負担する福利厚生にまつわる費用がかさむというのが現状といえるでしょう。
家族手当を廃止する企業が増えている背景
家族手当を廃止する企業が増えている背景として挙げられるのが、働き方の多様化や成果主義の導入、社員間の公平性などがあると言われています。
共働き世帯の増加に伴うライフスタイルの変化の中で家族手当の必要性が問われるようになったり、成果主義ベースの賃金制度の導入が加速したりするなどの時代背景もあり、家族手当の支給を取りやめるという企業も増えている傾向です。
また、2020年4月に「同一労働同一賃金」に関わる法律が整備され、勤務形態や性別に関係なく公平に給与を支給しなくてはならないという動きになったのも、家族手当の廃止が加速したきっかけの一つにもなったと言われています。
出典:「 図表1-1-3 共働き等世帯数の年次推移 」(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/21/backdata/02-01-01-03.html)(2024年4月22日に利用)
家族手当を導入する場合の注意点
企業側が家族手当を導入する場合、従業員が安心して働き続けるためにも以下のことに注意しましょう。
不平等が出ないようにする
家族手当は上記の通り支給する企業が減少しており、縮小したり、廃止に踏み切ったりする企業が増えていく可能性があります。そのような背景のなか、家族手当を導入する場合は、従業員の間で不平等が生じないよう、考慮する必要があると言えるでしょう。
出典:「配偶者を対象とした手当に関する見直しが実施・検討された事例等」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000123734.pdf)(2024年4月22日に利用)
家族手当の不正受給
家族手当制度を導入した後も、不正受給を防止できるような対策をしなくてはなりません。
家族手当の不正受給問題は、刑法第246条の詐欺罪に相当する場合もあります。たとえば、「配偶者が働き始めて扶養から外れた」「子どもが家族手当の該当年齢でなくなった」など、企業が定めている家族手当の条件から外れる場合があるので、該当する従業員は速やかに報告が必要です。
また、企業側も家族手当の不正受給が起きないよう、定期的に従業員に確認のメールやチャットツールで扶養家族に関する確認を忘れてはなりません。
出典:「明治四十年法律 第四十五号 刑法」(e-Gov法令検索)(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045)(2024年4月23日に利用)
家族手当を廃止する場合の注意点
家族手当を廃止する際の注意点として、いくつかの重要な要素があります。
まず、家族手当は、従業員の福利厚生の一環として位置づけられているので、廃止に踏み込む場合、該当する従業員とその家族への影響を最小限に抑えるための対策をしなくてはなりません。
家族手当の廃止は、特に子どもが3人以上いるような扶養する人数が多い従業員は、家計にも影響を及ぼす可能性があるため、事前に影響評価を行い、状況を見ながら段階的に廃止を進めることも一つの手です。従業員を思いやりながら新しい制度に適応できるようサポートすることが重要といえるでしょう。
家族手当の廃止に踏みこむ場合、代替となる対策も検討しましょう。たとえば、家族手当分の金額を基本給に含めたり、他の福利厚生を強化したりすることで、家族手当の廃止による直接的な家計の影響を緩和していく必要があります。
また、家族手当の廃止に伴う制度の変更を進める際には、企業側が従業員に事前説明もなく一方的に廃止の連絡をするのではなく、従業員への十分な説明と意見を聞く機会を設けることが望ましいと言われています。これにより、変更に対する理解を深めることができ、従業員の不満や不安を事前に解消できるでしょう。
以上の点を踏まえ、家族手当の廃止を検討する際は、従業員の声に耳を傾けながら、家族手当の廃止を計画的に、かつ円満に実施することが求められます。
家族手当の代わりになりうる制度
家族手当を廃止する代わりの制度を設ける企業も出てきています。たとえば、配偶者手当を廃止して、子どもの教育費にフォーカスした「子女教育手当」、従業員のIT系の資格取得を支援する手当「資格手当」は、家族手当の代わりとなるのではないでしょうか。
また、家族手当や住宅手当といった一定条件を満たした者のみが支給される手当を撤廃し、従業員の能力によって基本給を定める企業も出てきており、従業員がフェアな立ち位置で働ける環境を整えているケースもあります。
これからも家族手当の代わりとなる制度が登場するかもしれないので、各企業の制度の情報や動きに注目してみましょう。
より自社に合う制度設計を
諸説はありますが、家族手当は大正時代に作られた制度と言われています。令和になった今、従業員のライフスタイルが多様化し、家族手当の見直しや廃止をすることで、より公平さに重きを置いた制度を見直して、整えるという動きが出ています。
従業員が満足し、持続可能な働き方ができるよう、社会情勢の動きや自社の従業員の状況を踏まえ、他社の事例を参考にしながら自社にとって最適な手当制度を考えてみてはいかがでしょうか。

