人材不足が叫ばれる現代日本において、従業員全員が長く働き続けられる環境を作り、離職を減らすことは、企業を成長させていくために必要不可欠です。
そんな中、「リテンションマネジメント」に近年注目が集まっています。企業の魅力を高めて人材の流出を引き留めるこの手法について詳しく解説します。
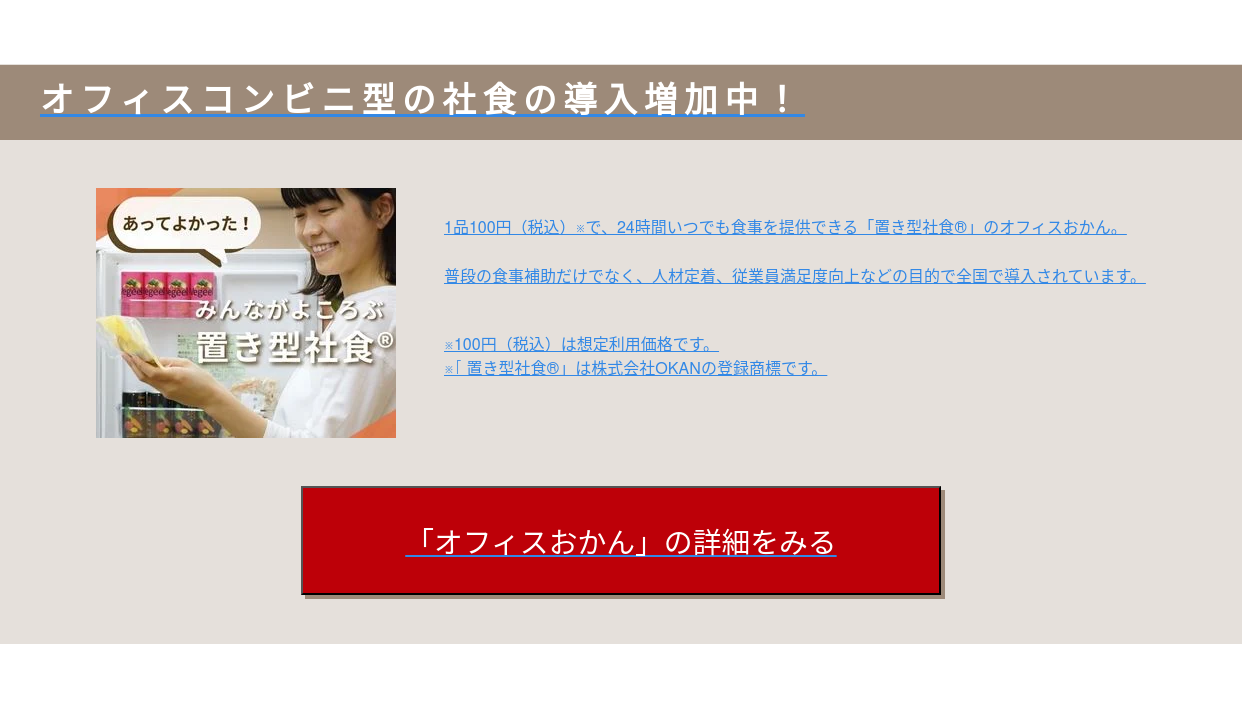
リテンションマネジメントとは?
リテンションマネジメントは、維持・引き留めを意味する「リテンション(retention)」と人事管理に使われる「マネジメント(management)」を組み合わせた言葉で、人材定着・従業員活躍のための管理手法を指します。自社に所属する従業員が長く働き続けられるようにするためのヒントとなる考え方です。
リテンションマネジメントについて、一部の専門家は「優秀なハイスキル人材を定着させる方法」と定義していますが、この記事においてはハイスキル人材かどうかに関わらず「自社に所属するメンバー全員が、長く働き続けられる方法」として取り扱います。
人材定着を行うことは、従業員にとっても、企業にとっても多くのメリットがあります。そのためには、長く働き続けられる環境が整った組織作りが重要となるのです。
なぜ今リテンションマネジメントが注目されるのか
なぜ今、リテンションマネジメントが注目されているのでしょうか? そこには、現代の日本全体が抱えている社会問題や、雇用への考え方の変化が関係していました。
人材不足
人材不足や労働力不足は、日本のあちこちで叫ばれています。少子高齢化で10代後半~60代の「労働力となる世代」の人口が減少し、高齢の従業員は退職してしまうため、結果的に人材不足に陥っているの状態です。
また、求職者の数よりも求人の数が多い、いわゆる「売り手市場」であることも人材不足の原因となっています。
離職率が高い・人材定着しにくい
終身雇用があたりまえだった時代とは違い、今では「労働条件が悪い」「人間関係や社風が合わない」と感じたら転職する、という考え方が一般的になり、新卒社員の3年内離職率は30%以上とも言われる時代です。
出典:「新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)を公表します」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00005.html
)(2023年10月25日に利用)
そんな現状から、多くの企業が人材定着のための施策に取り組んでいるようです。厚生労働省の「平成30年若年者雇用実態調査の概況」によれば、何らかの対策を実施しているのは実に72%の事業所でした。
![]()
この調査から、「職場での意思疎通の向上」「本人の能力・適正にあった配置」「採用前の詳細な説明・情報提供」といった対策をとっている企業が多いことが分かります。しかし離職率は依然として高いまま。つまり、各企業が取り組んでいるリテンション施策は、効果的ではない可能性があるということです。
では、どのようなことを意識すると効果が出やすいのでしょうか? ここからは実際にリテンションマネジメントに取り組むときのポイントをご紹介していきます。
出典:「5 若年労働者の定着について」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/4-21c-jyakunenkoyou-h30_05.pdf)(2023年10月25日に利用)(調査主体:厚生労働省、調査対象:全国の日本標準産業分類(平成 25 年 10 月改定)に基づく次の 16 大産業 〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)〕のうち、①事業所調査:対象となる上記に掲げる産業に属し、5人以上の常用労働者を雇用する事業所のうちから、産業別、事業所規模別に層化し、無作為に抽出した事業所を調査対象として 9,455 事業所 ②個人調査:上記アの事業所調査の対象の事業所において就業している若年労働者(15~34 歳の労働者)のうちから無作為抽出した若年労働者を調査対象として数 19,889 人に実施したアンケート調査、複数回答可、集計計測期間:①事業所調査:2018年9月22日~10月15日 ②個人調査:2018年10月11日~11月30日。)
施策へ取り組むことによるメリット
リテンションマネジメントに限ったことではありませんが、新たな施策を取り入れる際にはまず目標(ゴール)を見据えるべきです。
そのために、まずはリテンションマネジメントに取り組むメリットを確認しましょう。
採用コストを抑えられる
従業員が離職するたびに新たな人材を採用するのは、企業にとって大きなコストがかかってしまいます。採用にかかる費用や時間はもちろん、人事に携わる従業員にも負担が増えてしまう結果に。
離職者を減らして人材定着率を上げることで、こういった採用に関わるコストを抑えることが可能になります。
教育コストを抑えられる
新たな従業員が入社すれば、その人に対する教育や研修を行う必要があります。会社についての基礎的な研修から、実際の業務を行いながら指導するOJTまで、その教育にはもともと勤めている従業員の力が必要不可欠です。
採用コストと同じく、教育にかける費用や時間といったコストは、人材定着率を上げることで抑えられるようになります。
長期的な事業計画が立てられる
事業を成長させていくためには、長期的な事業計画を立てる必要があります。そしてその計画を実行するためには、必要なマネジメント力を持った人材が社内にいるか、もしくはこれから採用できるかといった点も重要です。
人材の入れ替わりが少なければ、従業員それぞれのスキルや適性を正確に見極めることができ、長期的な事業計画を立てる際に確実性が生まれやすいです。
企業イメージの向上につながる
離職率が高い企業は、「人が定着しないのは企業の体質に問題があるからでは」と思われてしまう可能性があります。特に就職活動を行う学生は、企業のイメージを非常に気にする傾向があり、離職率が高い企業にはマイナスイメージを抱いてしまいます。
反対に、離職率が低い企業には「それだけ働き続けたくなる企業である」というプラスイメージがつきやすくなります。これは就活生だけでなく、顧客から見ても良いイメージとなるでしょう。
労働生産性の向上
人材が入れ替わるたびに、業務の引き継ぎや教育・研修などの業務が発生すると、既存の従業員の業務圧迫に繋がり、精神的にも負担がかかってしまいがちです。
また、業務に慣れ効率的に動けるベテラン従業員が多くなるほど、労働生産性の向上につながりやすくなります。
顧客満足度の向上
顧客にとっても、同じ従業員が担当し続けることは信用につながります。「いつも同じ人が担当してくれるから、話が早い」という安心感は大きいもの。
人材定着率を上げることは、従業員同士だけでなく顧客との信頼関係も築き上げ、顧客満足度の向上という大きなメリットも期待できます。
10の要素を意識して人材定着率を上げよう
リテンションマネジメントを構成するのは、以下の10の要素です。それぞれ取り組んでいければ、離職者を減らし人材定着率を上げることが可能になります。
1. 福利厚生
利用できる福利厚生の数と質を充実させることは働きやすさにつながり、転職を思いとどまらせる効果があります。
2. 従業員満足度の向上/エンゲージメント
従業員にとっては、企業に対する満足度が高く企業風土への思い入れがあるほど「ここで働き続けたい」と感じるもの。社内でのコミュニケーションが良好だとエンゲージメントが高くなり、ハラスメントの防止にもつながります。
3. ワーク・ライフ・バランス
仕事と生活のバランスがとれるかどうかは、働きやすさに大きく関わってきます。労働時間が長すぎないかや休暇の取りやすさ、働くママへの支援策、副業の認可など、従業員一人ひとりが調和のとれた働き方を実現できる環境を作ることが大切です。
4. 健康/メンタルヘルス
身体的・精神的に健康な状態でなければ、長く働き続けることは考えづらいものです。定期的な健康診断の実施や、従業員の健康状態や心理的状態が分かるツールの導入など施策を行い、従業員の健康管理に配慮しましょう。
5. 働く環境・制度の整備
働くオフィスの環境や出勤に関する制度の整備を行うことも、リテンションマネジメントの施策として有効です。環境整備としては、コミュニケーションスペースの設置や、オフィスをフリーアドレス制にするといった方法が考えられます。リモートワークや時短勤務など、柔軟な働き方に対応できる出勤制度も働きやすさにつながります。
6. 適正な評価
業務に対して適正な評価をするため、上司が部下の人事評価を行うという従来の制度ではなく、同僚や部下を含む多方面の従業員が対象者の人事評価を行う「360度評価」もいい施策と言えます。
7. 報酬
報酬の改善も、非常に有効なリテンションマネジメント施策と言えるでしょう。スキルや経験に見合った給与体系になっているか、評価するパフォーマンスの定義づけは問題ないか等を見直すことは、企業にとっても従業員にとっても大きなメリットがあります。
待遇改善策のひとつとして、持ち株制度を導入するのもいいでしょう。
8. マネジメント
従業員の希望やスキル、経験、キャリアプランを踏まえた配置を行うためには、上司と部下とのコミュニケーションが必要不可欠です。面談の機会を増やしたり、メンター制度を導入することで、コミュニケーションをとりやすくなり、より一人ひとりに合ったマネジメントを実行できるようになります。
9. 育成・能力開発
従業員の育成や能力開発は企業にとって有益なものですが、従業員にとってもやりがいや成長を感じられ、働き続けようというモチベーションにつながります。
従業員それぞれの目標管理を行う、キャリアパスに合わせたジョブローテーションなどで適正な配置を行うといった施策も有効です。
10. 採用からのオンボーディング
新人を組織の一員として戦力化し定着させる一連の流れは、その後働いていくためのモチベーションに大きく関わってきます。新人研修を全体オリエンテーションのみで行うのではなく、定期的に短いサイクルで実施する1on1ミーティングなどの活用も有効です。職場全体で受け入れていくことで、早期退職を防ぎましょう。
実際の企業事例を参考にしよう
クックパッド株式会社|「料理」で生まれるコミュニケーション
クックパッド株式会社は、レシピ投稿・検索サービス「cookpad」を運営する企業です。毎日の料理を豊かにするためのサービスを提供するため、生鮮ネットスーパー「cookpad mart」なども展開し、様々な事業に挑戦しています。
同社は、従業員の主体的な活躍を支援するための制度やカルチャーが充実しています。
- レンタルスペースを活用し、社員同士で「料理」をしながら交流
- 他部署の業務を約2か月間体験できる「社内留学制度」
- コアタイムを設定しないフルフレックス制
- 5人以上集まったら申請できる「部活動」の活動費用をサポート
- グローバル人材育成のため、新卒入社3年目までの希望者に「海外での研修制度」を用意
特に「料理」の取り組みは、クックパッド株式会社ならではですね。コミュニケーションが生まれる場にもなっており、従業員満足度の向上に役立っているようです。
(参照:クックパッド株式会社「クックパッドについて(https://cookpad.careers/about/)」『採用情報 | クックパッド株式会社』、参照日:2023/10/26)
株式会社ヒューゴ|3時間の昼休み「シエスタ」で仕事の効率アップ
株式会社ヒューゴは、大阪に本社を構えるITコンサルタント企業です。Webサイトの運営や設計、プログラミングなどの技術を提供しています。
同社では、自由な働き方を支援する制度を取り入れています。
- 13時~16時の3時間を自由に過ごせる昼休みとする「シエスタ(仮眠)制度」
- 2018年から「テレワーク制度」を導入し、より自由な働き方が実現可能に
なんといっても特徴的なのは「シエスタ制度」です。昼食後の眠くなる時間帯に長めの休憩時間をとることでリフレッシュし、午後の業務に集中でき効率がアップするのだとか。
この3時間に仮眠をとるのはもちろん、ジムへ行ったり映画鑑賞をしたりと過ごし方は自由です。在宅勤務でもこの制度は有効で、非常に自由な働き方を可能にする制度と言えるでしょう。休憩が長い分終業時間も遅くなりますが、シエスタタイムに休まず仕事をして早く帰ることもできるそうです。
(参照:大阪産業創造館「「3時間の昼休憩」で仕事のパフォーマンスアップ(https://bplatz.sansokan.jp/archives/6991)」『Bplatz | 大阪産業創造館 中小企業情報サイト「ビープラッツ」 』、記事更新日: 2016/09/02、参照日:2024/02/29)
カネテツデリカフーズ株式会社|丁寧な「マンツーマン」に
カネテツデリカフーズ株式会社は、主にかまぼこやちくわなどの練り製品を取り扱う食品製造会社です。一時期、離職率の高い時期がありましたが、制度や企業の風土を変えることで、離職率を10%以下にまで低下させています。
- マンツーマン指導「新入社員への指導員制度」を導入
- 1か月に一度「面談」を実施し、現状の確認と今後の方向性などを一緒に考える
- 若手の先輩社員が指導にあたることで「新人・若手両方の育成」に
風土を変えるのは簡単なことではありませんが、同社は教育の仕組みを変えることで離職者の数を大幅に減らしました。
(参照:カネテツデリカフーズ株式会社「新人社員研修(https://www.kanetetsu.com/pages/recruit-training)」『おいしさ、ココロとカラダに。カネテツデリカフーズ株式会社』、参照日:2023/10/26)
(参照:公益財団法人兵庫県勤労福祉協会ひょうご仕事と生活センター「カネテツデリカフーズ株式会社(https://www.hyogo-wlb.jp/case/item356)」『ひょうご仕事と生活センター 』、参照日:2023/10/26)
サイボウズ株式会社|「働き方宣言」で働く場所も時間も柔軟に
サイボウズ株式会社は、ビジネス向けのグループウェアやクラウドサービスを開発から販売、運用まで行う企業です。同社は従業員一人一人のライフスタイルを尊重し、働き方改革に取り組んでいます。
- 働く場所も時間も従業員が考え、実現する「働き方宣言制度」
- 企業への断りなしでも「副業」が可能
- 子どもを預けられないといった問題に対応する「子連れ出勤制度」
- 「社内イベント」や「部活動支援」を実施
柔軟な働き方への対応はもちろん、社内でのコミュニケーションを生み出すための施策もあり、長く働き続けられる仕組みが数多く作られています。
(参照:サイボウズ株式会社「ワークスタイル(https://cybozu.co.jp/company/work-style/)」『サイボウズ株式会社』、参照日:2023/10/26)
自社の課題を見つけて離職者を減らそう
人材の定着率を上げるには、今いる従業員が「どうすれば長く働き続けたいと思うか」を考え、リテンションマネジメントを実施することが大切です。そのためには、柔軟な働き方や社内コミュニケーションの活性化、福利厚生の充実など、さまざまなアプローチが考えられます。
そのアプローチをどのように行えば良いかを考える起点となるのが、「自社の課題を知る」ことです。そこで有効になってくるのが、社内の不満の見える化を行うサーベイツールです。
株式会社OKANが運営する、組織改善サーベイツール「ハタラクカルテ」では、組織課題の可視化が可能です。ぜひご活用ください。

