行動指針とは、企業が持つ価値観や組織が目指すべき方向を示したものです。従業員が業務を行う際の道標となります。「改まって意識したことがない」という人もいるかもしれませんが、行動指針は企業としての成功と成長に寄与するだけでなく、従業員の働きがいにもつながり得る重要なものなのです。
そこで今回は、行動指針の定義や企業が定めるメリット、作成方法などを幅広く紹介します。社内における行動指針の浸透方法も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
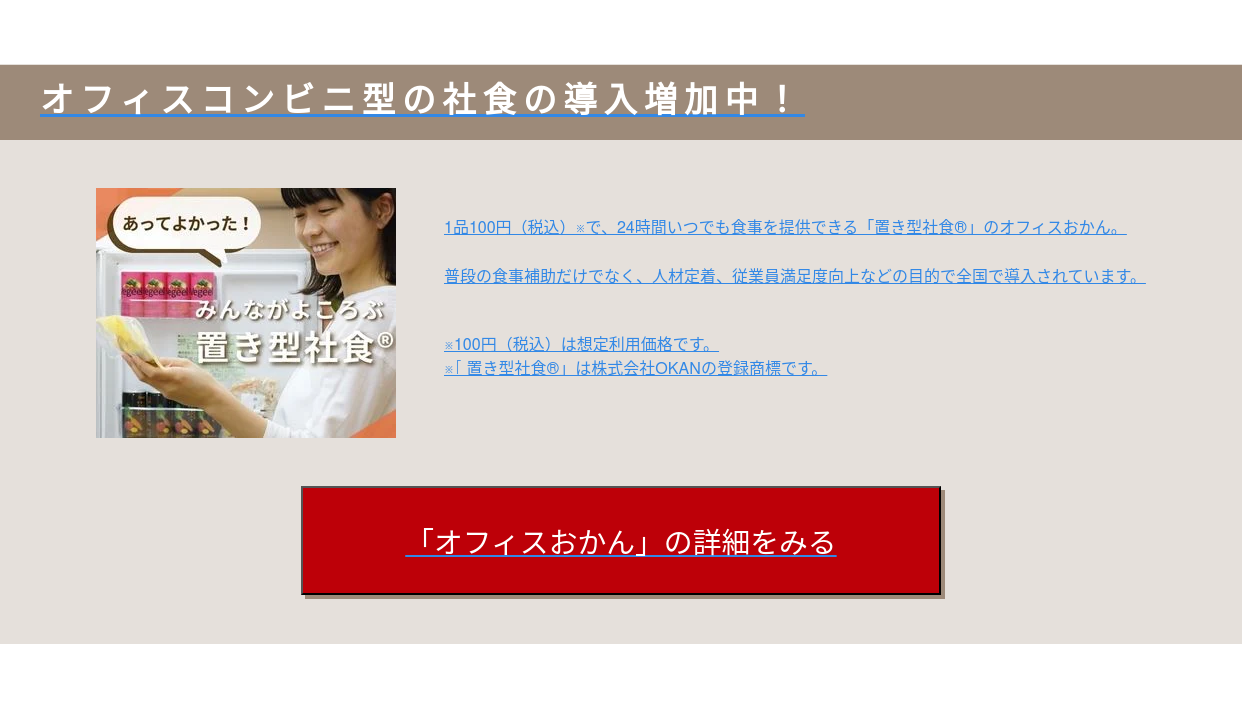
行動指針とは?
行動指針とは、ある行動を行ううえでどのような道を進むべきか、どのような態度をとるべきかを決めるための基準となるもののことです。企業によってどのような行動方針を掲げるかは異なりますが、基本的には従業員が業務を遂行するうえでの行動基準としたり、企業としての意思決定をするときの羅針盤としたりすることを目的としています。
行動規範との違い
企業のなかには、「行動指針」ではなく「行動規範」としているところもあります。いずれも従業員としてふさわしい行動や態度をとるための基準になるものですが、あえて違いをつけるとするなら以下のように定義しておくと良いでしょう。
- 行動指針:従業員が業務を遂行するときの大まかな基準となるもの
- 行動規範:その企業で働く従業員として業務をする際に必ず守るべきルール
どちらかというと、行動規範のほうが強制力があるといえます。
行動理念との違い
行動指針に似た言葉で「行動理念」というものもあります。行動理念は「その行動を行う理由」、つまり目指す先のことを指しています。
行動理念は「顧客満足度の向上」といった比較的抽象的なものに対し、行動指針は「どんなことをして顧客満足の向上を図るか」というHOWの部分を指すものです。具体的には「お客様の心に寄り添ったコミュニケーションをする」、あるいは「お客様ファーストで物事を考える」といったものが挙げられます。
行動理念は基本的な概念、行動指針はそれを成し遂げるための具体的な行動と考えればわかりやすいでしょう。
企業が行動指針を定めるメリット
多くの企業が独自の行動指針を掲げていますが、そこにはどのような意図があるのでしょうか。ここでは、企業が行動指針を定める2つのメリットをご紹介します。
企業としての価値観が統一できる
企業が行動指針を定めて全体に共有することで、組織としての価値観が統一できます。行動指針をきっかけに優れた組織文化が醸成されれば、従業員同士の信頼やつながりが生まれ、企業としての力がより強固なものになるでしょう。組織としての一体感が生まれることは、企業や事業成長の観点で大きなメリットなのです。
また、前述したように、行動指針は「企業としてどういった行動をとるべきなのか」を判断するための基準になります。
従業員としてどんな行動をとるのが適切かという共通認識があれば、裁量のある仕事を任せやすくなり、結果として主体性が育まれます。社員一人ひとりの行動は顧客対応の水準にも関わってくるため、うまく整備されれば顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
従業員のモチベーションアップにつながる
従業員のなかには、「評価されること」をモチベーションに頑張る人もいるでしょう。
従業員が組織に適切に評価されるためには、企業にとってプラスになる行動や判断を選択する必要があります。しかし、このとき判断基準になるものがなければ、選択にブレが出てしまったり、迷いが生じてしまったりするものです。仕事がスムーズにいかなくなり、モチベーションが下がってしまうかもしれません。
行動指針によってとるべきアクションや判断が明確になれば、迷うことも少なくなり、仕事がしやすくなるでしょう。指針に沿った行動を継続してとることで、適切な評価を受ける可能性が高まります。企業にとって正しいことをおこなえている、評価に値する行動をとれたという自負から、モチベーションの向上が期待できるのです。
行動指針の作り方5ステップ
ここでは、行動指針の基本的な作り方を下記の5つのステップに分けて紹介します。
1. 事業を通して実現したい理想を明確化する
2. 理想を現実にするために必要な行動を具体化する
3. 理想の実現に反する行動を挙げる
4. 内容を精査する
5. 行動指針を簡潔な言葉で表す
「行動指針を作成したいけど、何から始めたら良いかわからない」という人はぜひ参考にしてください。
1. 事業を通して実現したい理想を明確化する
まずは、事業を通して実現したい理想を明確にしましょう。事業によってどんな社会を実現したいのか、どんな問題を解決したいのかなどが挙げられます。組織として一貫性を持たせるために、企業理念やMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)をベースにするのもおすすめです。
2. 理想を現実にするために必要な行動を具体化する
続いて、1で明確にした理想を実現するために必要な行動をリストアップします。納得感のある行動指針にするため、ブレストの意味も兼ねてできるだけたくさんの行動を挙げていきましょう。理想は抽象的なものになりやすいですが、そのためにとるべきアクションを具現化することで、行動指針の方向性を定めやすくなるはずです。
3. 理想の実現に反する行動を挙げる
行動指針を策定するときは、理想の実現に反する行動を挙げることも重要です。例えば、倫理的に問題のある行為や企業理念に一致しない行動などが考えられます。行動指針の方向性がより明確になるだけでなく、従業員が企業の価値観に反する行為を行うリスクを抑えることにもつながるでしょう。
4. 内容を精査する
行動指針のベースが完成したら、その内容を精査します。ここでは具体性や実行の可能性、一貫性などを確認しましょう。役員や従業員などに壁打ちをして、実際の業務や組織文化に適しているかフィードバックをもらうのも一つの手段です。ブラッシュアップを加え、企業に関わる人にとって納得感のある内容に仕上げてください。
5. 行動指針を簡潔な言葉で表す
最後に、行動指針を簡潔な言葉で表します。一般的に行動指針は、従業員にとってわかりやすく、かつ印象に残りやすい言葉であるのが望ましいです。必要な情報は網羅しつつも、冗長すぎない表現で表すための工夫をしましょう。なかなか思い浮かばない場合は、他の企業の事例を参考にするのもおすすめです。
行動指針を従業員に浸透させる方法
当たり前のことですが、行動指針は策定して終わりではありません。従業員に浸透させ、実際にそれに沿った行動を起こしてもらう必要があります。ここでは、行動指針を従業員に浸透させる方法を5つ紹介します。
行動指針作成の背景やプロセスを発信する
従業員には、完成した行動指針だけでなく、作成の背景やプロセスも合わせて発信しましょう。
発信方法は、社内報やチャットなど、従業員がよく見ているツールを利用するのが効率的です。どのような思いで作られたのかがわかれば、行動指針への理解を深めるきっかけにもなります。このとき、経営陣が自らの言葉で伝えるのも効果的です。
目につく場所に行動指針を掲示・掲載する
行動指針を認識し、覚えてもらうためには、従業員の目に触れる機会を増やすのも効果的です。
完成した行動指針を社内向けポータルサイトやオフィスなどに掲載してみてください。行動指針をいつでも確認できるように、小さな冊子やカードにしたり、名刺に加えたりするのもおすすめです。可能であればデザイナーと協力し、目を引くクリエイティブに落とし込むのも良いでしょう。
日々の仕事の中に落とし込む
従業員に行動指針を浸透させるためには、目に触れる機会だけでなく、実際に使う機会も増やすことが大切です。
例えば、行動指針に沿って日報を運用したり、定例会議で行動指針に紐づいた話をしたりなどが挙げられます。行動指針を日々の業務レベルに落とし込めれば、自然と浸透していくでしょう。
研修やワークショップを開催する
社内でのリソースがあれば、定期的に行動指針に紐づいた研修やミーティング、ワークショップなどを開催するのもおすすめです。対象者を新卒社員、中途社員、管理職従業員などに細かく分けて行うと、それぞれの段階にあったアプローチを実施できます。効率的なインプットにもなるので、ぜひ試してみてください。
評価制度に紐付ける
従業員に行動指針を認識・理解してもらうには、評価制度に紐づけるのもおすすめです。
行動指針に沿ったアクションをとった人、あるいはインパクトのある成果を出した人に対して表彰や昇給などの形で評価することで、当人だけでなく他の従業員にもポジティブな影響を与えられるでしょう。自身が望む評価のために、積極的に行動指針を理解するチャンスになります。
行動指針を策定し、企業理念の実現につなげよう!
行動指針は、企業としての価値観を統一させて組織成長を促すだけでなく、従業員一人ひとりのモチベーションアップにもつながる重要な考え方です。
企業として実現したいことと紐付けて策定することで、一貫性のある内容になります。企業が持つ理想を実現するためにやるべきことだけでなく、「すべきでないこと」にも配慮するとより良い行動指針になるでしょう。行動指針策定後は、組織全体に浸透させるために工夫を凝らし、ポジティブな変化を与えていくことが大切です。
ぜひこの記事で紹介した内容を参考に、行動指針を定めてみてください。

