2019年4月から順次施行されてきた「働き方改革」により、労働者の働く時間やオフィス環境など、職場環境のさまざまな要素が変化してきました。今や働きやすい職場を作ることは、多くの企業で必須だと考えられているでしょう。
現状を考えると、労働者の働きやすさに直結する職場環境の改善には、まだまだ余地があるのではないかと考えられます。本記事では職場環境の改善に向けて、そもそも職場環境とは何かをおさらいしたうえで、職場環境を改善する3つのポイントについて紹介します。
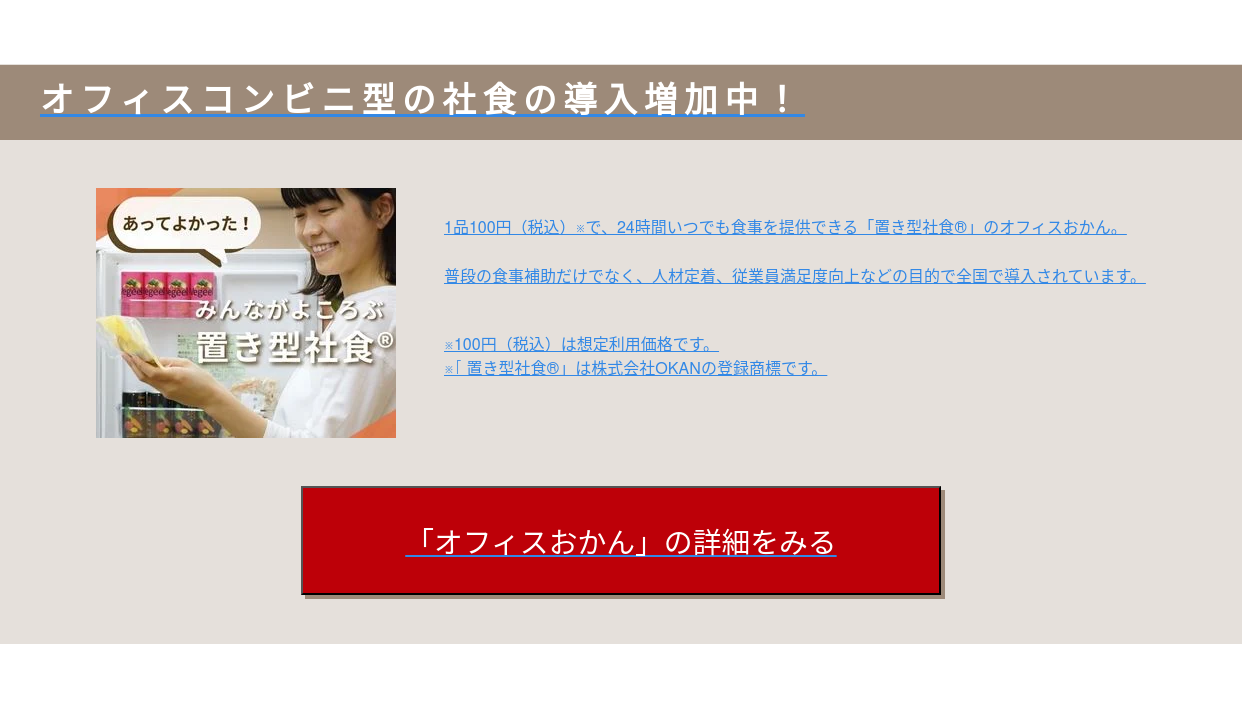
職場環境とは?3つの環境に関する条件
職場環境とは、労働者が就業する職場の環境諸条件のことをいいます。具体的には以下の3つの条件があるといわれています。
① 気候条件
職場において体に感じる温度、湿度、風速、気圧、コピー機などの機械による放射熱などが気候条件です。体に合わない気候条件で不快感を感じ続けると、健康によくないとされています。
② 物理的条件
照明、色彩、振動、粉塵、彩光、超音波、有害放射線など、物理的に五感が刺激され不快になる刺激が物理的条件です。物理的と言っても、目に見えないものの影響もあるので注意しましょう。
③化学的条件
化学的条件といって、ガス、蒸気、液体または固体由来の有害物質やにおいなど、化学物質などによる刺激が慢性的な不快感を与えることもあります。
社員の不満に繋がる上記の要素は、心身の健康を害する恐れがあります。せっかく仕事をする社員もイキイキと働くことは難しいでしょう。
良い職場環境では、社員が心身ともにイキイキと働けるだけでなく、仕事の効率化や質の向上、業績の向上にも繋がります。職場環境の改善を試みることは社員個人だけでなく、企業にとっても非常にメリットがあることです。
また、近年ではこれに職場の「人間関係」も条件だとする考え方も存在します。例をあげると、「雑談がしづらい」「有給休暇が申請しにくい」「育休が取りづらい」「ピリピリした雰囲気」などです。これらの要素も社員の心身の状態に影響するとして問題視されています。
職場環境改善の効果とは
職場環境改善の大きな効果は、社員の抱えるストレスが軽減されることです。企業が職場環境改善を行うことで、社員の不調の減少に期待できます。個人を対象にしたストレス対策に加えて職場環境を整えれば、健康状態の改善やストレスの解消などが期待できるでしょう。
結果として、従業員の仕事のパフォーマンス向上も見込めるため、職場全体として生産性がアップする可能性があります。会社の業績をあげるためにも、職場環境の改善は重要なポイントのひとつであることを認識しておくべきです。
職場環境の条件
快適な職場の条件とは一体何があるのでしょうか? 実は、目指すべき職場環境の指針が、法律で決まっています。以下では、職場環境を考えるうえで、職場環境に関係する法律と、それに基づいた快適職場指針がどういったものかも確認しておきましょう。
法律で定められている配慮義務
職場環境に関係する法律は、昭和47年に労働安全衛生法という法律が定められました。労働安全衛生法の第3条には、以下のように記載されています。
“事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。”出典:「労働安全衛生法」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74001000&dataType=0&pageNo=1)(2024年5月3日に利用)
つまり、上記の法律は、就労中の安全や働く人の健康を守り、快適な職場環境を作っていくことを促す内容といえます。労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の促進と形成を目的とした内容となっています。
快適職場指針
また、上記の法律に基づいた配慮が実際にきちんとなされるように「快適職場指針」が平成4年に定められました。快適職場指針では、対策を講じるべき視点として「作業環境」「作業方法」「疲労回復支援施設」「職場生活支援施設」の4つに分けて記載しています。内容としては以下の通りです。
作業環境
不安となることがないように、きれいな空気の確保、適切な室温や湿度の維持、明るすぎず暗すぎない調光など。
作業方法
労働者への心身の負荷の影響を考え、不自然な姿勢の改善や、大きな負荷がかかる力作業の見直しなど。
疲労回復支援施設
疲労やストレスなどを癒せるように、リフレッシュルームや相談室、作業後のシャワー室などの設置や整備。
職場生活支援施設
職場で快適に過ごせるような、清潔なトイレや洗面所、食堂、給湯室や談話室などの設置や整備。
また、職場環境を改善をするにあたり、継続的かつ計画的な取り組みや、労働者の意見の反映、個人差への配慮、潤いへの配慮を考慮して進めていくべきとも示されています。
出典:「職場のあんぜんサイト」(厚生労働省)(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo11_1.html)(2024年5月3日に利用)
良い労働環境を考えるポイント
実際に良い労働環境とは何かを考えるうえで、以下の3つのポイントについて検討してみてはいかがでしょうか。
自社の分析
自社に今何が足りないのか、自分なりに分析してみましょう。4つの要素「作業環境」「作業方法」「疲労回復支援施設」「職場生活支援施設」について、自社が何をしているか・何が不足しているか書きだしてみましょう。
実際に書きだしてみると、不足している点や自社の利点、改善すべきポイントが見えてきます。もちろん、自分が働いていて不満に思うことや満足している所を考えてみるのも参考になるでしょう。
職場アンケートの実施
自分で考えてみるのはもちろん大切ですが、自分では気づかないところが他の社員にとっては不満だった!なんてことも。そうなっては社員全員のための労働環境にはならないですよね。より客観視するために、アンケートを実施してみましょう。
ただし、個人が特定されるような状況だと本音で話せないことも出てくるので、匿名で回収するなどの配慮は大切です。また、得たアンケートと自己分析の結果を照らし合わせてみて重なるところは、本当に重要な項目だと考えられます。例として以下のようなアンケート項目が挙げられます。
- 労働時間は適切か
- 休憩時間は十分か
- 意見を言える場所や機会はあるか
- (室温や騒音など)快適に業務に取り組めるか
- (力作業や精神衛生上)無理な仕事の仕方をしていないか
- トイレや作業場は清潔に保たれていると思いますか
労働時間や実際に業務する環境、制度など、包括的な内容で作成してみましょう。
他企業を参考にしてみる
意外とどの企業も悩みは同じ、ということも。また、自社では出てこなかった斬新な制度や環境作りをしている企業もあるので、参考にしてみましょう。厚生労働省職業安定局による「働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する調査」では、労働時間や仕事のきつさなどを定量的にみることができます。
出典:「職場のあんぜんサイト」(厚生労働省)(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo11_1.html)(2024年5月3日に利用)
また、Great Place to Work® Institute Japanが行う「働きがいのある会社」ランキングに掲載されている企業を参考にするのもよいのではないでしょうか。
(参照:株式会社働きがいのある会社研究所「2024年度版 日本における「働きがいのある会社」ランキング ベスト100(https://hatarakigai.info/ranking/japan/2024.html)」、『働きがいのある会社研究所』参照日:2024/05/03)
職場環境改善のための具体的なアイデア
職場環境改善のためには、次のような企業の具体的なアイデアを参考にすることが有効です。
業務・勤怠管理をしっかりと行う
たとえば、残業代未払い防止のためには、勤怠記録をしっかり管理することが大切です。勤怠記録を「見える化」するために、インターネットを利用した勤怠管理システムを導入するという選択肢もあります。
働いている時間を可視化することで、どの業務にどれくらいの時間がかかっているのかや業務負担の偏りなども見えるようになります。職場環境の改善のための基礎となる作業になるでしょう。
残業を減らす
業務効率化の一環として、残業時間を減らす試みも必要です。会議やメールなどひとつひとつの業務・ツールについて「本当に必要なのか」を問うとよいでしょう。
本当に必要な場合であっても、時間を減らすなどの効率化はできます。会議なら参加人数や時間を見直す、結論を出すことを必須とする、などの工夫で効率化は可能です。見直しを行ったものは、効率が上がったかを検証し、従業員の意識に影響があったかについて分析することも大切です。
人事評価
人事考課の見直しも重要です。従業員への人事考課が適切でない場合、働く意欲へも影響しかねません。具体的には、評価の基準は公平で周知されているか、評価が報酬に結びついているか、といった点の見直しが必要です。
有給休暇を取得しやすい環境の整備
有給休暇についても、制度はあるものの実際には取りにくい状況であれば改善したいものです。1日だけでなく連続で有給休暇を取ると、特別休暇が与えられる制度を導入した企業もあります。有給休暇の取得率がアップすれば、従業員がリフレッシュしやすくなり、働く意欲も向上するでしょう。
コミュニケーション活性化
従業員同士のコミュニケーションの機会を積極的に設けることも、職場環境改善になります。株式会社OKANが全国の働く男女3760人を対象に行った 「withコロナで変化する「働くこと」に関する調査」によれば、人々が働くうえで最も大切にしているのは「良好な人間関係」という結果になっています。

(調査主体:株式会社OKAN、調査対象:全国の20~50代の働く男女を対象として3,760名に実施したアンケート調査、複数回答可、集計計測期間:2020年8月。)
たとえば、定期的にランチ代を支給して、従業員同士がランチに出かけるよう促進する施策もおすすめです。食事をしながら会話が弾めば、仕事の際もスムーズにコミュニケーションをとれるメリットがあります。
さらに、少し長めの休憩時間を取り入れる企業もあります。あらかじめ指定した曜日で、昼食後の数時間を休憩に費やせると、従業員は休息や運動など思い思いの過ごし方でリフレッシュでき、仕事による疲労が蓄積されにくくなります。紹介した実例を参考にしつつ、柔軟に取り入れていくことができれば、職場環境改善は順調に進むことでしょう。
福利厚生サービスを活用する
職場環境を整えるために、福利厚生を活用する方法もあります。オフィス内で提供されている福利厚生サービスには以下のようなものがあります。
- 食事サービス
- オフィスコーヒー
- オフィスマッサージ
- オフィスチェア購入
上記のようなサービスを活用することで、職場への満足度がアップするでしょう。
職場環境改善に取り組む際の注意点
職場環境改善に取り組む場合には、効果的な改善策を打ち出すために注意しておきたいポイントがあります。
まず、担当者を決めてマニュアルを整備し、随時見直しをしながら継続的に取り組むことが必要です。長期的な計画のもとに行われなければ、改善の成果は明確にならないでしょう。
また、職場環境改善では、従業員の意見をできるだけ反映させなければなりません。従業員が意見を出す機会を用意する必要があります。
さらに、従業員の年齢や好みはさまざまで、快適と感じる環境には個人差があることにも注意すべきです。室内の温度や空調、照明などについても、個別の配慮をすることも大切でしょう。職場環境改善で求められるのは、従業員全員の快適さを基本としながらも、一人一人への配慮も忘れずに対応する姿勢です。
自社にマッチするかの視点をお忘れなく
本記事では、職場環境改善に向けてのポイントを紹介しました。1番大切なことは自社の労働者にとって本当に良い労働環境とは何かを考えることです。
まずは分析やアンケートから自社の労働環境を把握してみるとよいでしょう。他の企業がどういう背景で職場環境の改善に取り組んでいるかを良く確認し、自社の社員にも当てはまるかどうか、実現可能かどうかを十分に検討したうえで取り入れてみるのはいかがでしょうか。

