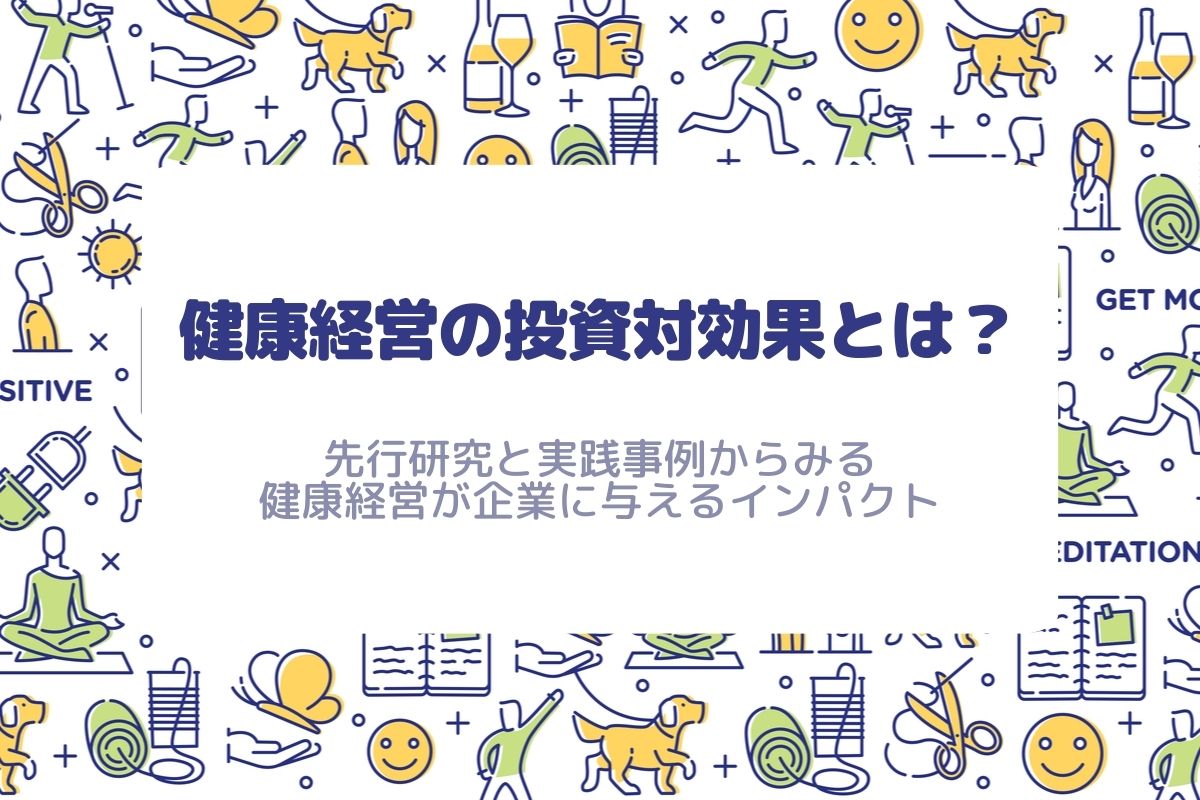健康経営銘柄、健康経営優良法人などの認定制度が注目され、企業が主導して従業員の健康をサポートする「健康経営®︎」。新型コロナウイルス流行下においても、健康経営の効果が発揮されている調査も発表されました。(詳細は後述します)
健康経営を行うことで、企業の投資対効果はどの程度なのでしょうか。国内の先行研究や健康経営に積極的な企業事例をもとに、健康経営のインパクトをご紹介します。
※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
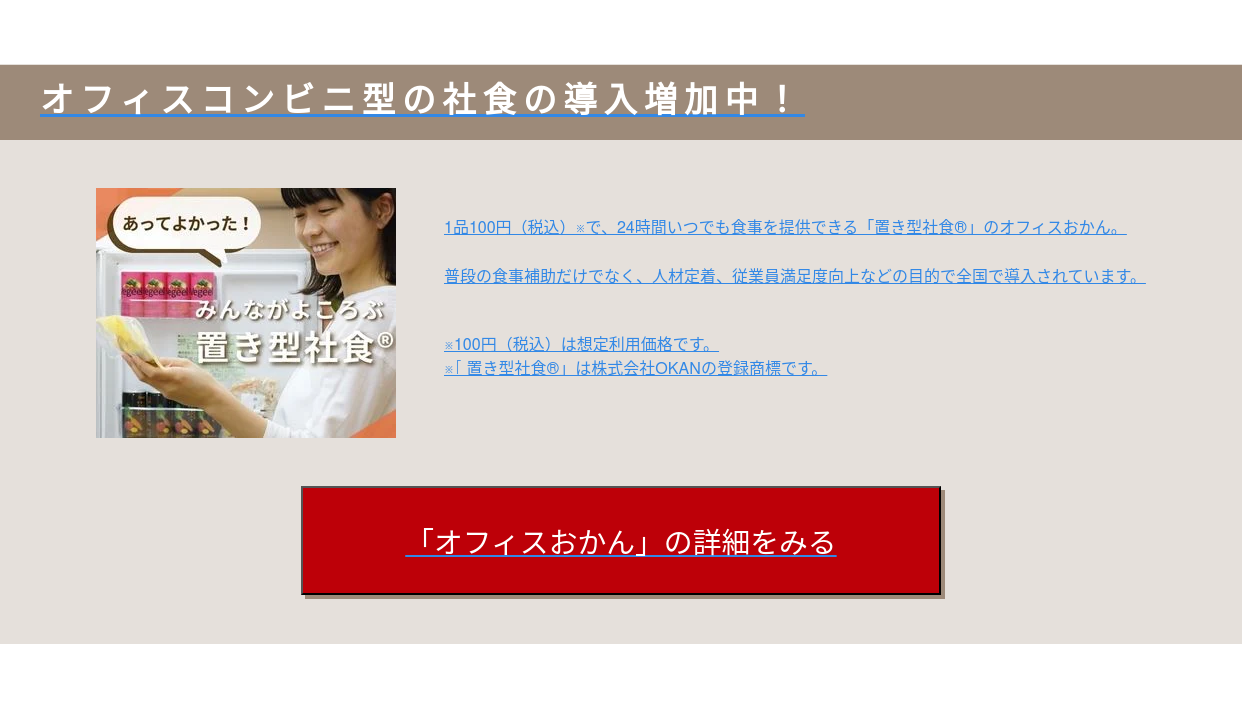
健康経営とは?
健康経営は、1992年にアメリカの心理学者ロバート・H・ローゼンが自身の著書によって提唱した概念です。従業員の健康管理を企業が取り組むべき経営上の問題と捉え、積極的に健康増進への取り組みを行っていく経営手法のことをいいます。
英語ではHealth and Productivity Managemen、企業・組織の従業員の健康(Health)と生産性(Productivity)の両方を同時に追求していくことを指します。
関連記事
健康経営とは?メリットや成功に導くポイントを解説!
健康経営促進事例・サービスまとめ|従業員が利用する福利厚生は?
コロナ禍における健康経営の影響
コロナ禍をきっかけに、健康を重要視する人が増えています。実際に健康経営に積極的に取り組み、健康経営銘柄や健康経営優良法人の認定を受けた企業は、どのような影響があったと考えているのでしょうか。
健康長寿産業連合会の調査によると、健康経営銘柄2020、健康経営優良法人2020等の認定を受けた企業のうち75%が良い影響があったと回答した一方で、未認定企業では42%でした。
健康経営の取り組みを通じて良い影響を受けることはもちろん、それらの取り組みを通じて従業員本人の健康に対する意識が上がったことも予想できます。コロナ禍で自身の体調を細やかに配慮することが増えたとき、同時に日頃の健康に対しても配慮する習慣がついたのであれば、企業全体としてもプラスの影響になったのではないでしょうか。
(参照:株式会社ルネサンス「新型コロナウイルス流行下における健康経営の取り組み状況に関する調査結果を公表(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000027019.html)」『PR TIMES』、記事更新日:202/7/29、参照日:2023/11/13、調査主体:健康長寿産業連合会、調査対象:健康長寿産業連合会 加盟企業・団体を対象として44法人中、 36法人に実施したアンケート調査、単一回答、集計計測期間:2020年6月8日~6月15日。)
関連記事
【全解説】健康経営優良法人とは?|メリット・申請方法認定基準を紹介
期待される効果
健康経営の効果としては、従業員が健康で長くイキイキと働くことができるようになることが挙げられます。そこからさらに、短期的効果・長期的効果に分けることができます。
短期的効果の例
- 従業員の健康増進/意識改善
- 組織の活性化
- 生産性向上
- 人材の定着/離職率低下
- 優秀な人材の確保
長期的効果の例
健康経営の効果検証
短期的な効果は見られたとしても、予算・費用をかけて取り組むからには、長期的効果である「業績の向上」に関してどのぐらいのインパクトがあるのか気になるところです。
そこで、先行研究や実践企業の結果から健康経営の費用対効果の一例をご紹介します。
健康経営と企業業績の相関関係
厚生労働省が発表した資料では、健康経営度調査における上位評価20%の企業の株価時価総額を見ると、TOPIX(東証株価指数)の平均を上回る水準で推移していることがわかりました。
健康経営とは、従業員の健康促進に対し経営的な投資をする企業を見える化し、社会的に評価をする制度です。そのような企業は今後の成長の可能性が見込まれ、株価上昇の一助になっていることが読み取れます。経済産業省によると、特に健康経営銘柄では、企業の長期的な活躍を重視する投資家に対して魅力的な企業として紹介することを目的にしています。
このことから、 健康経営に力を入れている企業は、業績も良いという一定の相関関係があることがわかるのではないでしょうか
出典:「健康経営」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html)(2023年11月13日に利用)
出典:「「健康経営銘柄2023」に49社を選定しました!」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230308003/20230308003.html)(2023年11月13日に利用)
![]()
出典:「データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000171483.pdf)(2023年11月13日に利用)
健康状態がどれくらい経済損失に繋がっているか
日本における健康経営の先駆け的な企業であるDeNAでは、過去に社内のプレゼンティーズムによる損出がどのくらいあるのかを計算しました。
プレゼンティーズムとは、体調や心身が不調にもかかわらず会社に出勤することによって、本来持っている遂行能力が低下し、パフォーマンスを充分に発揮しきれない状態を意味します。同社によると、このプレゼンティーズムによる損出額は少なくとも20億円以上になったそうです。
病気や風邪などといった休息が必要な状態だけではなく、日頃の頭痛や肩こりといった一見些細な症状でも、業務の生産性が低下してしまうことがあります。こういった事態が積もりに積もることで、大きな損出に繋がってしまうのかもしれません。そのため、企業が従業員の健康をサポートすることは、このような損失を少しでも減らすことに寄与するでしょう。
(参照:一般社団法人 富山県経営者協会 「企業価値と健康経営(https://www.toyama-keikyo.jp/fueki_pdf/fieki9.pdf)」、参照日:2023/11/13)
健康リスクによる一人あたりの損失
経済産業省による、健康経営の生産性等へのインパクトについての研究では、個人の健康関連リスクの高さによって一人あたり30万円程度の損失が発生するとわかりました。
日頃の健康状態が、プレゼンティーズムやアブセンティーズム(心身の体調不良を原因とする遅刻や欠勤など)を引き起こし、その結果少なくない損出額を出してしまうのです。何か問題が発生してからではなく、そうならないための日々の取り組みが重要だということが分かります。
![]()
出典:「健康経営の推進に向けた取組」(経済産業省)(http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/yuuryouhoujin.pptx)(2023年11月13日に利用)
従業員のメンタルヘルスと利益率との関係
経済産業研究所の研究プロジェクトでは、従業員規模100人以上の451企業に対し、メンタルヘルスの不調が企業業績に与える影響を検証しました。その結果、メンタルヘルス休職者比率の上昇した企業は、それ以外の企業に比べ、中期的に売上高利益率の落ち込みが大きいことがわかりました。
休職者が増えることで、企業の労働力が減ることは容易に想像ができます。また、休職者が増え続けてしまう場合は、労働環境が整備されていないことと相関するケースが少なからずあるように思われます。そのような環境では、残された従業員も生産性高く業務に取り組むことが困難になってしまうかもしれません。さらに、そういった企業は組織内だけではなく、社会的にもマイナスに評価されてしまうことがあるようです。
(参照:独立行政法人経済産業研究所「企業における従業員のメンタルヘルスの状況と企業業績-企業パネルデータを用いた検証-(https://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/14j021.html)」『RIETI - 独立行政法人経済産業研究所』、参照日:2023/11/13)