少子高齢化、人材不足、過労死など、仕事に関わる社会問題の解決のために、政府主導の取り組みが本格的に始まっています。
なかでも重視される「ワークライフバランス(仕事と生活の調和)」は、今や多くの企業において求められる考え方です。新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大したことにより、より早急なワークライフバランスの改善施策が必要になったのではないでしょうか。
今回は「ワークライフバランスとは何か」「なぜ注目されるのか」といった基本から、実際に取り組んでいる企業の成功事例まで、詳しく紹介していきます。
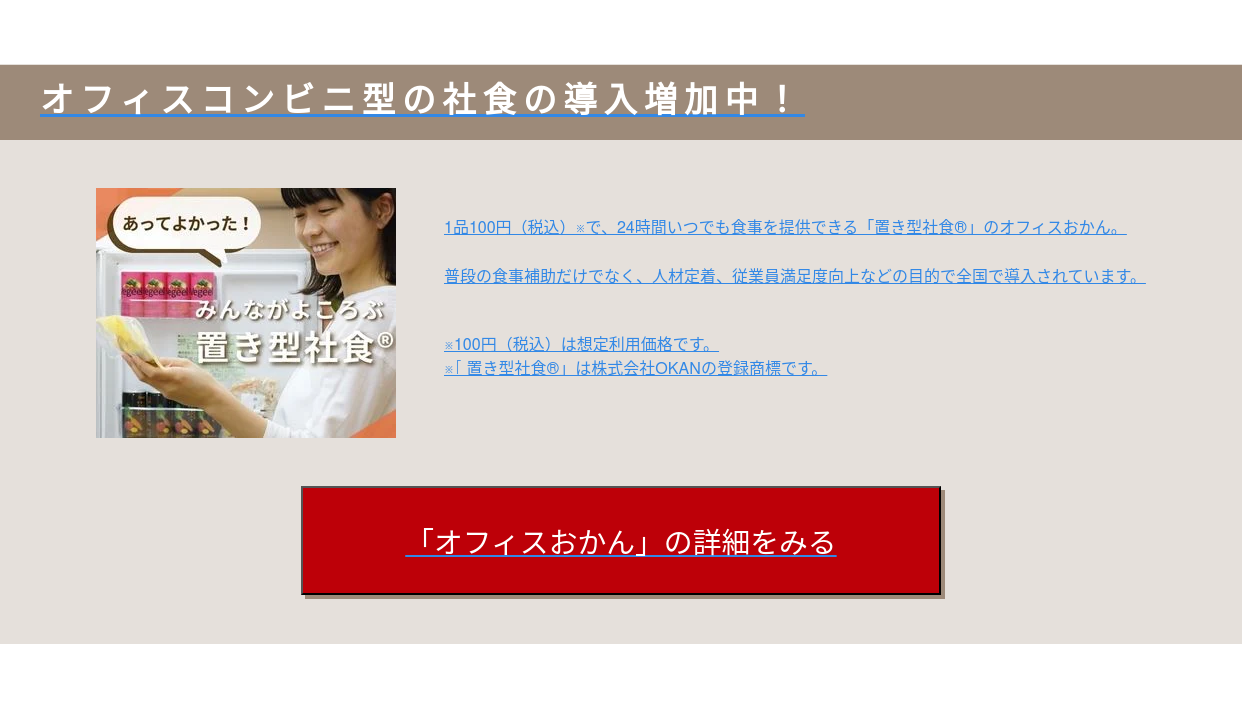
ワークライフバランスとは
ワークライフバランスとは、「仕事」と「仕事以外の私生活」をひとりひとりが望む形でバランスをとることを指します。
バランスというと、ワークとライフのバランスを同じくらいに揃えることだと認識しがちですが、内閣府サイトによれば「老若男女問わず誰もが、個人のライフスタイルの希望を実現できる」といったことを意味する言葉です。
出典:「仕事と生活の調和とは(定義)」(内閣府) (https://wwwa.cao.go.jp/wlb/towa/definition.html)(2023年10月10日に利用)
ワークライフバランスが普及した背景
そもそも「ワークライフバランス」のはじまりは、1980年代後半にアメリカで行われた「ワーク・ファミリー・バランス」というワーキング・マザー雇用策が発端です。
女性の社会進出により共働き世帯が一般的になってきた頃、アメリカでは産業構造の変化が起こり、人材確保が急務となっていました。そこで働きたい女性と働き手が欲しい企業とでニーズが合い、企業は女性のために仕事と家庭の両立支援策を講じるようになります。これが、アメリカ企業から自然発生的にはじまった「ワークファミリーバランス」とよばれる取り組みです。
その後、独身者や男性にも対象が拡大した「ワークファミリーバランス」は「ワークライフバランス」へと変化し、フレックスタイム制やテレワークなど、より効果的な施策とするための制度が生まれていきました。
出典:「Ⅳ 欧米諸国におけるワーク・ライフ・バランスへの取組」(内閣府) (https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/wlb/siryo/pdf/wlb11-3-1.pdf)(2023年10月10日に利用)
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章における目指すべき3つの社会像
政府が推し進めるワークライフバランスには、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」とよばれる基本的な取り決めがあります。
本憲章は、仕事と生活を両立しにくい状況を打開するための方針として策定されました。日本の社会経済構造が変化する一方で、人々の「働き方」に関する意識や取り巻く環境が追い付いていないという状況があるためです。
具体的には、仕事と生活の調和が実現した社会は、以下のような社会だと定められています。
就労による経済的自立が可能な社会
「就労による経済的自立が可能な社会」とは、これからの世代を担う若者が経済的に自立できる働き方ができ、結婚や子育てなどのライフプランの実現のために生活基盤を確保できる社会のことです。
健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会
「健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会」とは、働く人々の健康が保たれ、家族や友人などと充実した時間を過ごしたり、自己啓発・地域活動への参加のための時間を持てる社会のことです。
多様な働き方・生き方が選択できる社会
「多様な働き方・生き方が選択できる社会」とは、老若男女問わず誰もが自身の働き方や生き方に挑戦でき、子育てや介護など個人のライフステージに応じた多様な働き方と公正な処遇が確保されている社会のことです。
以上の内容が、政府が制定するワークライフバランスの定義です。これを踏まえたうえで、誤解されやすいワークライフバランスを正しく理解するためのポイントを見ていきましょう。
出典:「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」(内閣府) (https://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/20barrier_html/20html/charter.html)(2023年10月10日に利用)
出典:「仕事と生活の調和とは(定義)」(内閣府) (https://wwwa.cao.go.jp/wlb/towa/definition.html)(2023年10月10日に利用)
ワークライフバランスを正しく理解するためのポイント
「ワークライフバランス」という言葉を知ってはいるものの、正確な定義は分からなかったり、なんとなく仕事と生活のバランスをとるイメージを思いを抱いていたりする方が多いのではないでしょうか。
ここでは、ワークライフバランスを正しく知るために理解しておきたいポイントを紹介します。
年齢・性別を問わず全ての働く人が対象である
ワークライフバランスの取り組みは、育児をしながら仕事をする女性や、まだ仕事に慣れていない新入社員のためだと思われることがしばしばあります。
しかし、本来ワークライフバランスの定義には「働く人それぞれの望む形で仕事と生活との均衡を保つ」ことが含まれており、全ての人が等しく恩恵を受けられる取り組みとなっています。決して、一部の人のみにメリットのある施策ではないということを、まずは押さえておきましょう。
各々の価値観をもとにバランスを考える
ワークライフバランスの最も誤解されやすい部分といっても過言ではないのが、「従業員それぞれの価値観をベースとして考える」という点です。
よくある誤解としては、「仕事と私生活との割合を等しく分けると良い」「仕事とプライベートの境界線をハッキリとさせるのが良い」などが挙げられます。しかしこれでは、あらかじめ決まったバランスを押し付けるような形になってしまい、従業員ひとりひとりの思うような働き方を実現できるとは言えません。
例えば以下のような2者がいた場合、価値観が全く異なります。
A:好きなことを仕事にしている。あまり仕事と生活をはっきり分けるイメージはない。
B:仕事はあくまで手段。生計を立てるために働いているため、私生活とは分けたい。
そのため、働く人それぞれが持つ価値観ファーストで働き方を選べることがベストである、という考え方が必要になります。
ワークライフバランスが注目される理由
2019年に働き方改革関連法が施行されたことで、企業はフレックスタイム制や短時間勤務制度などの具体的な施策へ乗り出し始めています。
では、なぜ今ワークライフバランスの施策の必要性が高まっているのでしょうか。ここでは、ワークライフバランスに注目が集まる理由を、大きく3つの理由に分けて見ていきます。
人手不足の深刻化
まずはじめに挙げられるのが、「人手不足」です。
パーソル総合研究所による「労働市場の未来推計」によると、2030年には644万人の人手不足となると予測されています。労働力の大半を担っていた世代の高齢化と出生数の減少が重なり、企業側にとって人材確保は急務です。人手が足りないために一部の社員に大きな負荷がかかってしまい、社員のワークライフバランスが崩れてしまうことも少なくありません。
そのため、近年では人材定着のための 「リテンションマネジメント」を始める企業も増えています。また、女性や高齢者などの人材を多様な職種で生かす雇用も重視されています。そうした動きに伴って、ワークライフバランスを保つ施策の重要性が高まっているのです。
(参照:株式会社パーソル総合研究所「労働市場の未来推計 2030(https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/spe/roudou2030/)」『パーソル総合研究所』、参照日:2023/10/10)
関連記事
リテンションマネジメントとは?離職を防ぐ10つの要素と事例を紹介
共働き世帯の増加と女性の労働参加
次に、「共働き世帯の増加」と「女性の社会進出」が挙げられます。
総務省の「男女共同参画白書(2020)」を見ると、共働き世帯数が年々増加していることがわかります。さらに、1997年を境に専業主婦世帯数を上回ったのち、2012年には専業主婦世帯と共働き世帯とで大きな差が生じ始めています。
![]()
![]()
現在は、妻がパートタイムやフルタイムで働く共働き世帯が一般化しています。しかし、育児や介護などと仕事と両立するためには、社員自身の頑張りだけではなく、企業の理解や積極的な取り組みが不可欠なのです。
そういった移り変わりに応じるため、ワークライフバランスを実現する支援策が必要になったことが理由の一つであるといえます。
出典:「内閣府男女共同参画局「令和2年版 男女共同参画白書(概要)」(厚生労働省)(https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/gaiyou/pdf/r02_gaiyou.pdf)(2023年10月10日に利用)
教育費の増加
さらに、「教育費の支出」は年々増加し、大きな負担となっています。
バブル崩壊後に家計の支出総計は減ったものの、少子化による子供の総数の減少を考慮すると、一人当たり年間教育費は大きく増加していることが分かっています。
また、教育費負担に関する意識調査では、教育関連の費用が経済的負担の上位に位置しており、子育ての不安要因の7割が「経済的負担の増加」であるという結果が出ています。
こうした背景からも、共働き世帯が増えているのだと推測できます。今度、どのくらい教育費がかかるか先行きが不透明な中で、不安を抱えながら貯蓄を続けている家庭が多く存在しているのかもしれません。こうした不安に寄り添い、支援していくためにも、ワークライフバランスが注目されています。また、ワークライフバランスを実現する事で、少子高齢化を食い止めることにも繋がってくるかもしれません。
(参照:鈴木菜月「子どもの減少と相反する一人あたり教育費の増加 : 家計の消費構造の変化(https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/h30pdf/201817005.pdf)」『経済のプリズム』no.170、出版者:参議院、刊行年月:2018/7、参照日:2023/10/10)
出典:「内閣府「平成24年度「子ども・子育てビジョンに係る点検・評価のための指標調査」報告書 全体版 Ⅰ.子育て全般について」(内閣府)(https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/13024511/www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/cyousa24/shihyo/pdf/2-1.pdf)(2023年10月10日に利用)(調査主体:内閣府、調査対象:20 歳~59 歳のインターネット登録モニターを対象として10,000 名に実施したアンケート調査、集計計測期間:2012年10月12日~11月15日。)
働き方・ライフスタイルの多様化
2019年に施行された働き方改革が推進されたことで、個人の人生観やライフステージに合った働き方を選択できる社会への変革が求められるようになりました。一方で、そうした環境が整っている企業は少ないという状況でした。
しかし、東京都が2020年に行った調査によると、柔軟な働き方を実現するために導入された取り組みとしては、時差出勤制度が最も多く、次いでテレワークが続くなど、環境整備が進んでいることがわかります。特に、コロナウイルスの感染が拡大した時期は、多様な働き方を選択できるように多くの企業が制度の見直しを始めました。
(参照:東京都産業労働局「令和2年度 働き方改革に関する実態調査(https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/koyou/jouken/r2/index.html)」『東京都産業労働局ホームページ』、参照日:2023/10/10、調査主体:東京都産業労働局、調査対象:都内の常用従業者規模 30 人以上の 3,000 事業所、事業所調査の結果、協力を得られた事業所の正社員 2,000 人に実施したアンケート調査、集計計測期間:事業所は202年9月14郵送し10月12日を返信投函〆切、従業員は2020年10月16日、23 日、30日の3回に分けて事業所宛に郵送し、11月16日を返信投函〆切 。)
ワークライフバランスに取り組むメリット【企業視点】
ワークライフバランスの施策を実施する企業側には、どのようなメリットがあるのでしょうか。
従業員エンゲージメント向上による離職率の低下
慢性的な人手不足により、今いる社員の定着や新たな人材の確保は優先順位の高いことだといえます。
そうした状況のため、企業ならではのワークライフバランス施策を実施することが求められています。リテンションマネジメントの観点からも、ワークライフバランスを意識した施策を行うことは大きな意味を持っているでしょう。
関連記事
リテンションマネジメントとは?離職を防ぐ10つの要素と事例を紹介
企業売上の向上
ワークライフバランスの改善が従業員の生活を豊かにする反面、売上に良くない影響を与えかねないのではないかと考える企業もいるかもしれません。
しかし、厚生労働省の調査によると、ワークライフバランスの改善において実績を出している企業の方が、売上高の水準が高いことがわかっています。
![]()
一般に、国や自治体はワークライフバランスの改善に適切な配慮を行っている企業をモデルケースとして、認定や表彰を行っています。そこで、表彰の有無で売上高を比べると、確かに両者には差が生じていることが見えてきます。
従業員にとって働きやすい環境を提供することは、自社の利益に良い影響をもたらすことがわかります。従来、労働環境を整えることは、従業員の満足度や生産性向上に繋がると言われています。その結果、会社が活性化され良い効果を生み出してくれるのだと考えられます。
出典:「平成29年版 労働経済の分析 -イノベーションの促進とワーク・ライフ・バランスの実現に向けた課題- 第2節 労働生産性の向上とワーク・ライフ・バランスの実現に向けた企業の取組」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/17/dl/17-1-2-2_02.pdf#page=2)(2023年10月10日に利用)
企業イメージUPと雇用の増加
ワークライフバランスに配慮した制度を整えることで、長期的に見て企業のイメージが向上し、雇用の増加を見込むことができます。
例えば、女性・男性問わず育児のための制度を充実させれば、仕事と育児を両立したいという希望を持って職探しをしている人々にとって、条件の良い会社として選ばれやすくなります。さらに、利用しやすい制度が増えることで、有効的な利用につながり、社風にも良い影響を与えてくれるでしょう。
ワークライフバランスに取り組むメリット【従業員視点】
ここで、ワークライフバランスのための施策を実施したとき、従業員が受けられるメリットは何かを見ていきます。自社社員はどれだけのメリットを受けられているかチェックしてみましょう。
健康維持
ワークライフバランス施策の多くは、従業員の健康を守ることに繋がるでしょう。次々と重なる仕事に追われ、十分な休息をとれなければ、健康に害が及ぶのは目に見えています。働く上で、心身の健康は基本であり守らなければいけないものです。
従業員自身ではマネジメントしにくい仕事と生活のバランスを、企業側から積極的に守ってもらえることで、安心感も芽生えます。
プライベートの充実
ワークライフバランス施策は、従業員のプライベート充実にも繋がります。
企業によって異なりますが、スキルアップ休暇の取得や育児休暇の取得といった種類の異なる休暇制度の利用によって、仕事とプライベートの切り替えがしやすくなるといった効果も期待できます。
労働生産性の向上
心身の健康が向上することによって、副次的に労働生産性の向上も見込まれるでしょう。
多くの従業員にとって、自身の労働生産性を上げることは課題となっています。やみくもに仕事に打ち込むのも一つの手ですが、仕事とは全く異なる性質をもつ時間を過ごすことで、新しいアイディアが浮かぶことや効率的な方法が見つかることもあります。
ワークライフバランスの具体的な施策・取り組み例
ここまで、ワークライフバランスの概要や、施策を行うことで得られるメリットなどを解説してきました。では、実際に企業が実践すべきことは何なのか、具体的な施策や取り組みを紹介していきます。
残業時間の削減
ワークライフバランスにおける「ワーク」のバランスを調整するために出来るのが、残業時間の削減です。
2020年4月より中小企業にも「時間外労働の上限規制」が適用されます。政府主導の動きとは別に、企業独自でできる残業時間の削減方法を検討してみるのも良いかもしれません。まずは、現状の残業時間がどれだけ多いのか確認してみましょう。
有給休暇取得の促進
働き方改革の影響で、日本では有給取得率が改善しつつあります。2019年には過去最高の56.3%を記録しましたが、政府が目標とする70%にはまだまだ程遠い数字です。
しかし、企業の中には有給休暇をいかにして社員に利用してもらうか、工夫を凝らしている会社もあります。自社らしい工夫が有給休暇取得率を向上させる近道かもしれません。
出典:「10月は「年次有給休暇取得促進期間」です」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21144.html)(2023年10月10日に利用)
仕事と育児・介護の両立支援
仕事との両立が難しいといわれる育児と介護は、離職の大きな原因にもなっています。「この職場で働き続けたい」といった想いをもちながら、仕事を辞めるしかない人も少なくないでしょう。
人材確保の観点からも重要な育児・介護の両立支援を行うことで、多様な人材の確保につながることが期待できます。
テレワークの導入
新型コロナウイルス感染拡大がきっかけとなり、多くの企業で在宅勤務やテレワークの導入が進んでいますが、感染防止だけでなくワークライフバランスの取り組みとしても相性が良いのです。育児をしながら働くワーキングマザーや、毎朝の満員電車によるストレスで疲労する従業員などを支える有効な施策となってくれます。
柔軟な労働時間制の採用
離職防止や採用力の強化にもつながる、フレックスタイム制や裁量労働制なども従業員の働き方に大きく関わる施策です。業種によっては合う・合わないが分かれますが、取り入れやすい施策のひとつだといえます。
育児休暇の取得サポート
少子化の流れから育児に関するサポートは不可欠となってきているなか、共働き家庭にとって嬉しいのが育児休暇のサポートです。
2021年6月に成立した「改正育児・介護休業法」により、男女ともに子育てがしやすい環境が整ってきています。育児休業給付金などを活用しやすい環境を整えることで、従業員にとって働きやすい職場となっていくでしょう。
多様な正社員の登用
正社員と非正規雇用者の二極化を緩和するために求められる、職務、勤務地、労働時間を限定した「多様な正社員」制度の実現も有効な取り組みです。
育児、介護、その他の事情から転勤が厳しい場合は勤務地を限定する「勤務限定社員」、金融やITなど専門的な知識が求められる職務における「職務限定社員」、家庭と仕事の両立のため長時間労働が難しい場合の「勤務時間限定社員」などが挙げられます。
こうした正社員登用を実施することで、長年働くことのできるエンゲージメントの高い従業員の確保にもつながっていきます。
出典:「「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書をとりまとめました」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000052513.html)(2023年10月10日に利用)
福利厚生サービスの導入
仕事に熱意をもって取り組む従業員にとって、日々の家事や食事の準備は労力のいるものになっているかもしれません。仕事と生活との両立を助ける、家事代行サービスや食事の宅配サービス、ベビーシッター費用の補助などを福利厚生サービスとしてアウトソーシングすることも、効果的な取り組みになるはずです。
ファミリーデーの実施
ファミリーデーは、従業員同士の結束力向上はもちろんのこと、従業員の家庭内コミュニケーション促進にもつながります。普段どのような環境で働いているのかを家族が知るきっかけになり、子どもにとっても両親のことを知る良い機会になるでしょう。
経営層からのメッセージ発信
経営トップが率先してメッセージを発信していくことは、企業の規模に関わらず有効な施策といえます。
従業員にとって良い制度があっても活用されないまま、もったいないで終わらせずに経営者自らがワークライフバランスに取り組む姿勢を見せていくことが大切です。
定期的な制度の見直し
なかには、ここまでで挙げたような制度はもう導入しているという企業もいるかもしれません。その場合、自社従業員のニーズを捉えられていない可能性があります。
魅力的な制度があっても、実際に利用できる環境が整っていなかったり、そもそも制度自体を知らないということも考えられます。定期的に社内の制度を見直すことで、従業員に愛されるワークライフバランスの制度作りをしていきましょう。
ワークライフバランスを重視する企業の成功事例
有休休暇取得を促し自己研鑽へ繋げる|六花亭製菓株式会社
20年以上連続で有給休暇消化率100%という、驚異的な数字をもつ六花亭製菓株式会社。
1000人を超える従業員数ながら、「従業員一人ひとりが心も体も健康でなければ美味しいお菓子は作れない」というモットーを掲げ、全従業員の有給取得を達成しています。また、社外の活躍を表彰する制度では、従業員の積極的な自分磨きの場を広げるサポートもしています。
工場敷地内にある社内保育園には総芝生の園庭や走り回れるホールがあり、繁忙期には延長して運営するなど、従業員の子育て支援が充実しています。
【取り組み施策】
- 毎月各職場で活躍した人を表彰する制度
- 一人最大年間 20 万円まで補助が出る社内旅行制度
- 最長2ヶ月間の公休を自分磨きに使える公休利用法
- 家庭と仕事の両立を応援する社内保育園 など
出典:「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2011~新しい働き方で拓く。つながりのある日本社会~ 六花亭製菓株式会社における取組」(内閣府) (https://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/report-11/zentai.html)(2023年10月10日に利用)
(参照:株式会社六花亭「福利厚生・社内制度(https://www.rokkatei.co.jp/recruitment/outline/welfare/)」『六花亭』、参照日:2023/10/10)
社員それぞれに応じた柔軟な制度|東日本旅客鉄道株式会社
東日本旅客鉄道株式会社では、男女共同参画を3つの基本の考え方があり、その一つとして仕事と育児・介護の両立支援があります。
職業柄、不規則な勤務形態ということもあり、社員それぞれの事情に応じて利用できるような制度が用意されています。介護休職や短時間・短日数勤務制度といった基本的なものから、事業所内保育所でおむつ・ミルクの用意や洗濯代行を行うなど手厚い制度までさまざまです。
【取り組み施策】
- 3歳までの子を持つすべての社員が日中時間帯の6時間勤務が可能
- 小学校3年までの子がいる社員が月4日の育児・介護休日を取得可能
- 事業所内保育所での24時間保育日の設定 など
出典:「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2012 ~人も社会も意識を変えて。さらに進める働き方改革~ 「カエル!ジャパン」キャンペーン登録企業事例紹介 東日本旅客鉄道株式会社における取組」(内閣府) (https://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/report-12/zentai.html)(2023年10月10日に利用)
多様な働き方がしやすい環境|株式会社ニトリホールディングス
株式会社ニトリホールディングスでは、エリア限定総合職とよばれる「勤務地限定正社員」をはじめとする多様な働き方を提供しています。
育児・介護・配偶者の仕事の都合等の理由から転居ができない総合職社員に適用される制度で、これは契約社員、パート社員のステップアップとしても活用が進んでいる制度です。結果として、これらの施策により離職率の低下、女性活躍に大きく影響を与えることに繋がっています。
【取り組み施策】
- エリア限定総合職制度
- ホームタウン制度
- 社員群転換制度 など
出典:「株式会社ニトリホールディングス」(厚生労働省)(https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/cases/case_0093/)(2023年10月10日に利用)
ワークライフバランスから発展した概念「ワークライフバリュー(WLV)」
![]()
株式会社OKANには、ワークライフバランスならぬ「ワークライフバリュー(WLV)」という考え方があります。
多様な働き方が可能になったことにより、企業と個人とで求めるものにズレが生じてしまうことがあります。そこで、社員ひとりひとりが考えるバランスに着目し「バランスを正す」のではなく、「仕事と生活に関わる個人が大切にしたいと思う価値観を重視する」という考え方が生まれました。
ワークライフバランスを正しく理解して従業員満足度向上へ
ここまで、ワークライフバランスについての解説から、さまざまな企業の事例まで、具体的な内容を紹介してきました。
時代の変化と多様なニーズの登場により、企業に求められる制度も異なります。また、所属する社員の悩みの種類によっても、整備すべき制度の性質は異なるでしょう。だからこそ、自社社員がどのようなニーズを持っているのかを知り、社員が心地よく働くことができるような制度設計をしていく必要があります。

